獣医師コラム一覧
-
- 2025/12/16
- 犬や猫の噛み癖の理由...
-
- 2025/12/16
- 犬猫のよだれが多いの...
-
- 2025/12/09
- 犬の皮膚がカサカサ?...
-
- 2025/12/02
- 犬と猫の頻尿・血尿・...
-
- 2025/10/06
- 猫が毛玉を吐くのは病...
-
- 2025/10/06
- ペットロスの向き合い...
-
- 2025/10/06
- 愛犬の歩き方がおかし...
-
- 2025/10/06
- シニア犬、シニア猫(...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の成長に合...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の「社会化...
獣医師コラム
犬や猫の便秘について|放置は危険?原因・対策・受診のタイミング
倉敷市、岡山市、総社市、浅口市、玉野市、早島町の皆さんこんにちは。
岡山県倉敷市の倉敷動物愛護病院の院長垣野です。
愛犬や愛猫が便秘かな?と感じたとき、「少し様子を見よう」と考える飼い主様もいらっしゃるかもしれません。しかし、便秘は単なる一時的な不調ではなく、思わぬ病気のサインである可能性もあります。
特に、長期間にわたる便秘は犬や猫にとって大きな負担となり、放っておくと腸閉塞やその他の合併症を引き起こすリスクがあるため注意が必要です。
また、愛犬や愛猫の「普段の排便リズム」を知らないと、異変に気づきにくいこともあります。毎日の排便の回数や便の状態を把握し、少しでも違和感を覚えたら早めに対応してあげましょう。
今回は、便秘の定義や一般的な症状、便秘が引き起こす危険性、そして原因となる疾患について解説します。

■目次
1.便秘とは?正常な排便回数を知っておこう
2.便秘の原因
3.病院を受診すべき症状
4.診断方法
5.治療方法
6.予防方法と自宅でのケア
7.まとめ
便秘とは?正常な排便回数を知っておこう
便秘とは、「いつもの排便のリズムから大きく外れ、スムーズに排便できない状態」のことです。
便秘が長引くと、腸内に便が蓄積し、さらに便秘が悪化するという悪循環に陥ることがあります。重症化すると腸閉塞を引き起こし、緊急治療が必要になるケースもありますので、便秘を軽く考えず、早めに対処することが大切です。
そして、愛犬や愛猫の便秘に気づくためには、普段の排便リズムを把握しておくことが大切です。
<犬の正常な排便回数>
犬の排便回数は、一般的に1日1〜3回が平均とされています。
ただし、運動量や食事内容によって変動し、高齢犬や運動量の少ない犬は排便回数が減る傾向にあります。
<猫の正常な排便回数>
猫の排便は、通常1日1回程度が一般的です。しかし、食物繊維や水分の摂取量によっては、2日に1回でも正常範囲とされることがあります。 ただし、長毛種の猫は毛球(飲み込んだ毛)が影響しやすく、便秘になりやすいため注意が必要です。
便秘の原因
犬や猫が便秘になる原因はさまざまですが、以下のような要因が考えられます。
・水分不足(特に猫は水をあまり飲まないため、便が硬くなりやすい)
・食事の影響(食物繊維の不足・過剰摂取、フードの急な変更)
・運動不足(腸の動きが鈍くなり、排便がしづらくなる)
また、病気による影響も考えられます。
・骨盤骨折(過去のケガによる影響で、腸が圧迫されることがある)
・腫瘍(腸が圧迫されて便が通りにくくなる)
・椎間板ヘルニア(神経の圧迫で腸の動きが低下)
・会陰ヘルニア(高齢の去勢していないオス犬に多い)
・腎臓病(腎臓の機能が低下すると、水分の再吸収がうまくいかなくなる)
・甲状腺機能低下症や糖尿病など(代謝に関わる疾患も腸の動きを低下させ、便秘を引き起こす)
病院を受診すべき症状
便秘は一時的なものであれば様子を見ることもできますが、以下のような症状が見られた場合は、早急に動物病院を受診しましょう。
<緊急受診が必要な症状>
以下のような症状が見られる場合は、緊急性が高いため、できるだけ早く動物病院を受診してください。
・3日以上排便がない(腸閉塞の可能性)
・食欲が低下している(消化器や全身疾患の可能性)
・元気がなく、ぐったりしている(便秘が重症化している恐れ)
<早めの受診が推奨される症状>
以下のような症状がある場合は、重症化を防ぐためにも早めに受診を検討しましょう。
・排便時に痛みで鳴く
・コロコロとした硬い便が続く
・排便の姿勢をとるが、何も出ない
・お尻をしきりに気にする
診断方法
便秘の原因を特定し、適切な治療を行うためにさまざまな検査を実施します。
便秘の背後に病気が隠れていることもあるため、正確な診断がとても重要です。
<問診>
診察の最初に、便秘の原因を探るための問診を行います。スムーズな診断のために、事前に愛犬・愛猫の様子を観察し、以下のポイントを把握しておくとよいでしょう。
・既往歴の確認(過去の病気や手術歴)
・生活環境の確認(食事内容、運動量、飲水量など)
・排便の頻度、便の状態(硬さ、量、色など)
・その他の症状(食欲低下、嘔吐の有無、元気の程度など)
<身体検査>
問診の後、腹部の触診を行い、腸内のガスのたまり具合や腸の動き(蠕動運動)が正常かどうかを確認します。
また、排便時の痛みやお腹の張りがないかをチェックし、異常が疑われる場合はさらに詳しい検査を行います。
<画像検査>
便秘の原因が腸の詰まりや腫瘍などの物理的な問題にある場合、画像検査が非常に有効です。
・レントゲン検査:腸内のガスや便の詰まりの位置を確認し、異物誤飲の有無も調べる
・超音波検査(エコー):腸の動きや消化管の状態、腫瘍の有無を詳細に確認する
<血液検査>
便秘が全身疾患(腎臓病・甲状腺機能低下症・糖尿病など)と関連している可能性がある場合、血液検査を行います。
・食欲低下がある場合:脱水の有無や、炎症の兆候をチェックします。
・高齢の犬や猫の場合:腎不全や甲状腺機能低下症など、便秘の原因となる基礎疾患を調べます。
治療方法
便秘の治療方法は、原因や症状の重さによって異なります。
<対症療法>
・薬の処方
便が硬くなりすぎて自力で排出できない場合、便を柔らかくする薬や腸の動きを促す薬が処方されることがあります。
人間用の下剤は犬や猫には危険な場合があるため、自己判断で与えないようにしましょう。
・点滴治療(脱水対策)
便秘が続くと脱水を引き起こすことがあります。軽度であれば皮下点滴で水分補給を行いますが、重度の脱水では静脈点滴が必要になり、入院治療となることもあります。
・浣腸
便が硬くなりすぎて排出できない場合、獣医師が浣腸を行うことがあります。
市販の浣腸を自己判断で使用するのは危険です。成分によっては犬や猫に悪影響を及ぼすことがあるため、必ず獣医師に相談しましょう。
< 外科的処置>
便秘の原因が腸閉塞や腫瘍による腸の圧迫である場合、手術が必要になることがあります。
・腸閉塞
異物(おもちゃ、骨、毛玉など)が詰まり、便が通らなくなった場合、緊急手術が必要になることがあります。
・腫瘍による圧迫
腸や骨盤周囲に腫瘍ができ、便の通り道が狭くなっている場合は、腫瘍の摘出手術を検討することがあります。
・重度の会陰ヘルニア(去勢していない高齢のオス犬に多い)
直腸が本来の位置からずれてしまい、慢性的に便秘になることがあります。その場合、手術で修復する必要があります。
また、腎臓病やホルモン疾患などの病気が原因で便秘になっている場合は、まずはそちらの治療を優先します。
予防方法と自宅でのケア
便秘を防ぐためには、日頃のケアが非常に重要です。特に、食事・水分・運動・生活環境の4つのポイントに注意し、愛犬・愛猫が快適に排便できる環境を整えることが大切です。
<食事の工夫>
食物繊維は腸の働きを助けますが、不足しても摂りすぎても便秘の原因になることがあります。
犬の場合は、低繊維のフードを食べていると便秘になりやすいため、さつまいもやかぼちゃなど、消化しやすい食物繊維を適度に取り入れるのが効果的です。
一方で猫は、食物繊維を摂りすぎると便が硬くなり便秘が悪化することがあります。食事の変更は獣医師と相談しながら慎重に行いましょう。
<水分をしっかり摂る>
水分不足は便秘の大きな原因になります。便を柔らかくするために、飲水量を増やす工夫をしましょう。
・ウェットフードを取り入れる
・常に新鮮な水を用意する
・犬や猫が飲みやすい器を選ぶ
・循環式の給水器を使う(特に猫は流れる水を好むことが多い)
<運動をしっかり取り入れる>
運動不足は腸の動きを低下させ、便秘を悪化させることがあります。
犬の場合、散歩の時間や室内で遊ぶ機会を増やすことで腸の働きを促せます。猫は、キャットタワーやおもちゃを使って遊ばせることで、自然に運動量を増やすことができます。
<快適なトイレ環境とストレス管理>
猫はトイレの 場所や砂の種類に敏感 です。清潔に保つことはもちろん、安心して排泄できる環境を整えることが大切です。
犬も決まったタイミングで排便しやすい習性があるため、リラックスして排泄できる環境を作りましょう。
また、環境の変化(引っ越しや家族の増減など)があると、ストレスを感じやすくなり、便秘につながることがあります。 できるだけ普段と同じ生活リズムを保ち、落ち着ける場所を確保するなどの工夫をしましょう。
まとめ
愛犬や愛猫の便秘は一時的なものと思いがちですが、放っておくと腸の働きが弱くなり、健康に影響を及ぼすことがあります。
食事や水分、運動を見直すことで改善できることもありますが、便秘が続く場合や、食欲や元気がないときは早めに動物病院にご相談ください。
当院では、便秘の原因を詳しく診断し、適切な治療やケアのアドバイスを行っていますので、少しでも気になることがあればお気軽にご相談ください。
■関連する記事はこちらから
・犬や猫の下痢、病院に行くべきタイミングは?|症状の見分け方と受診の目安
岡山県倉敷市にある「倉敷動物愛護病院」
ペットと飼い主様にとって最善の診療を行うことを心がけております。
一般診療はこちらから
獣医師コラム一覧
-
- 2025/12/16
- 犬や猫の噛み癖の理由や原因は?...
-
- 2025/12/16
- 犬猫のよだれが多いのは異常?正...
-
- 2025/12/09
- 犬の皮膚がカサカサ?秋冬の乾燥...
-
- 2025/12/02
- 犬と猫の頻尿・血尿・排尿困難に...
-
- 2025/10/06
- 猫が毛玉を吐くのは病気?|毛球...
-
- 2025/10/06
- ペットロスの向き合い方~飼い主...
-
- 2025/10/06
- 愛犬の歩き方がおかしい?犬の椎...
-
- 2025/10/06
- シニア犬、シニア猫(7歳以上)...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の成長に合わせた食事...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の「社会化期」にすべ...
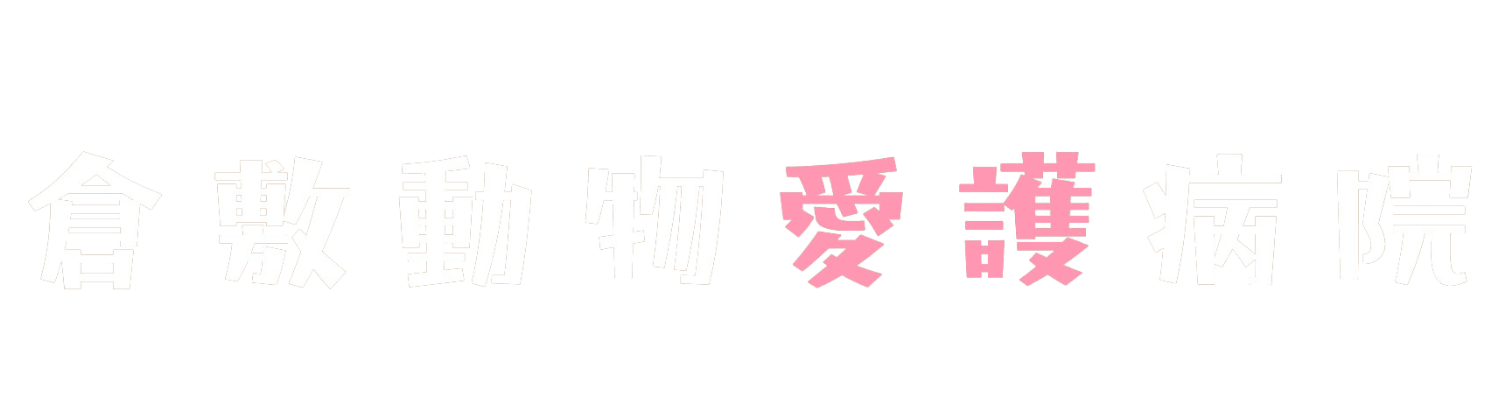
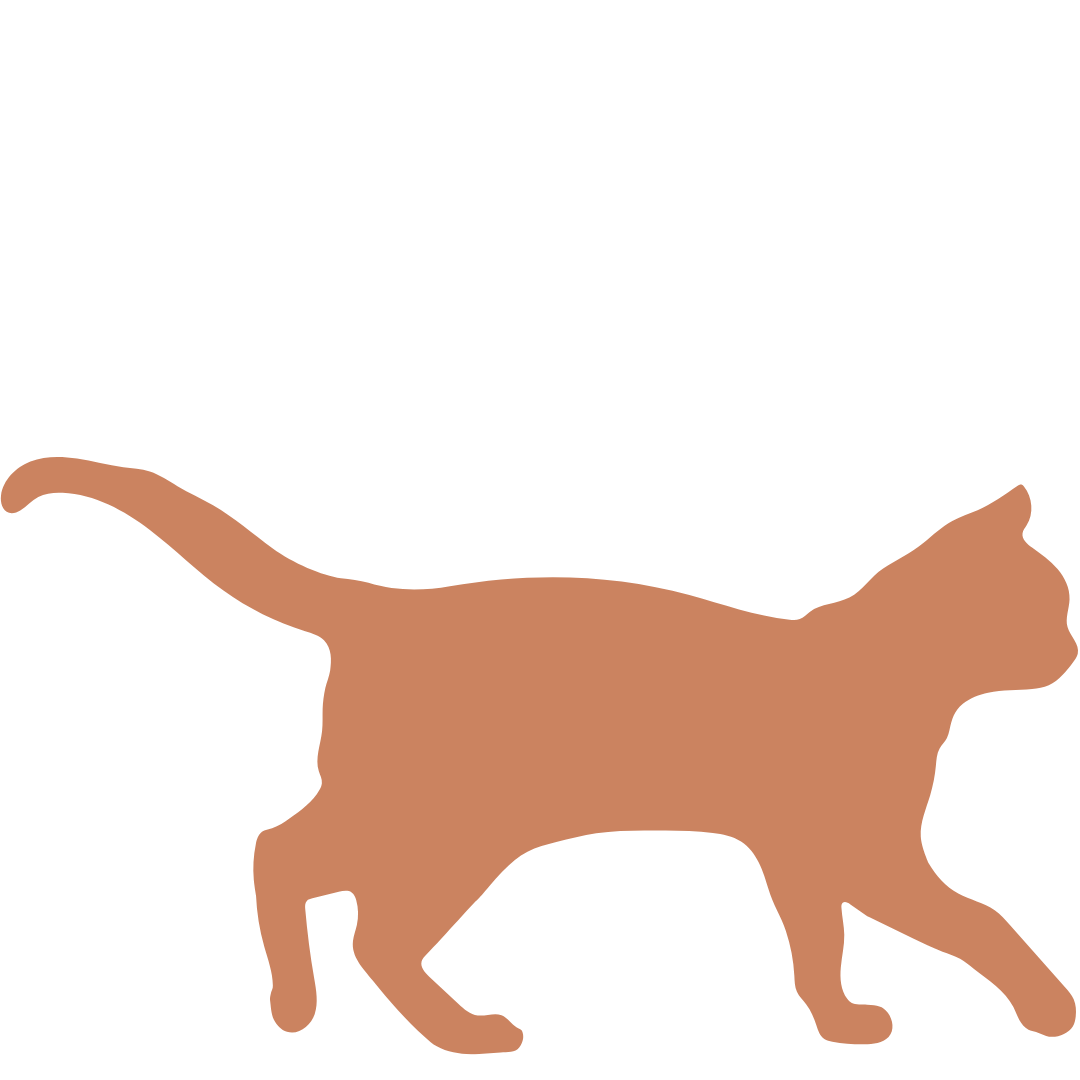
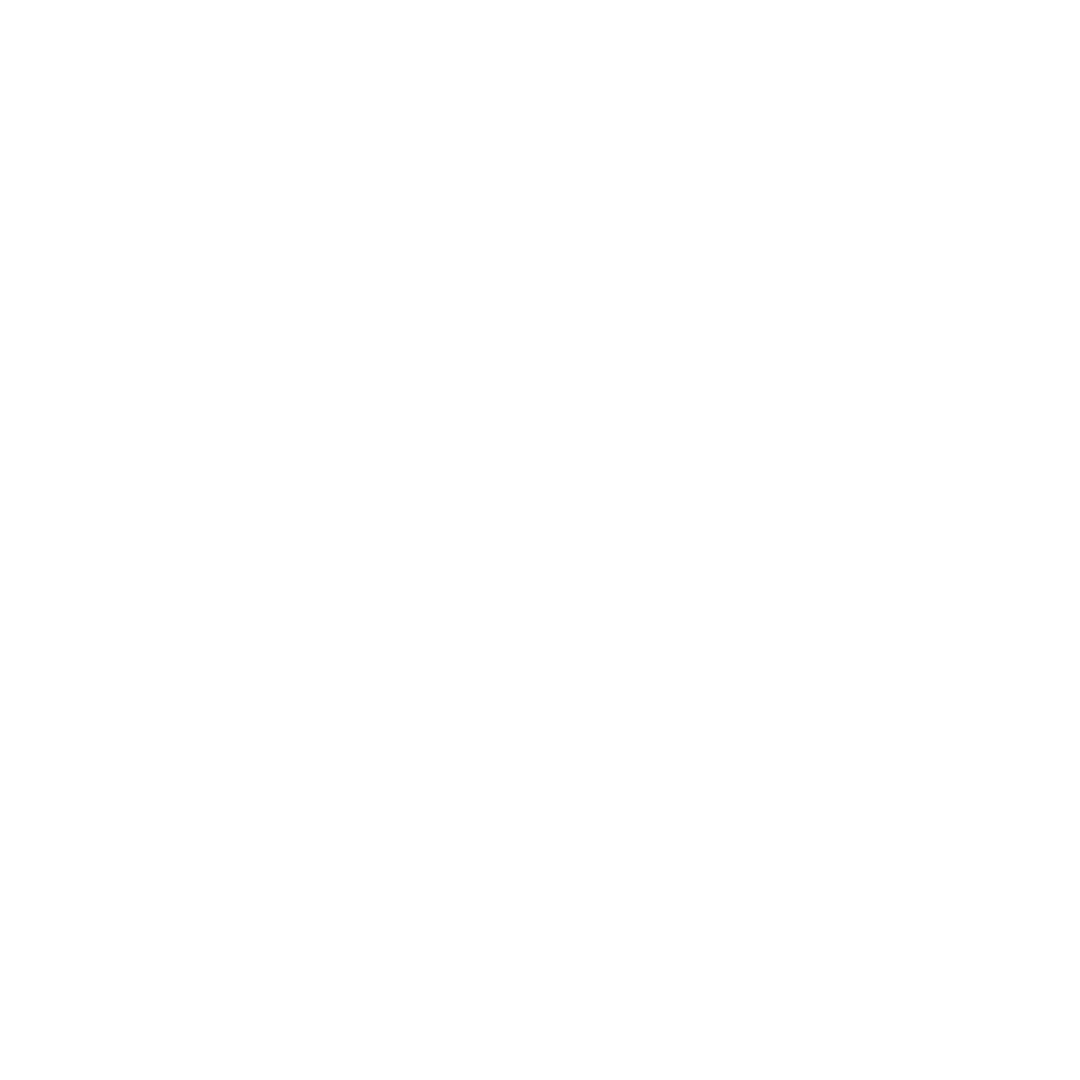
 インスタグラム
インスタグラム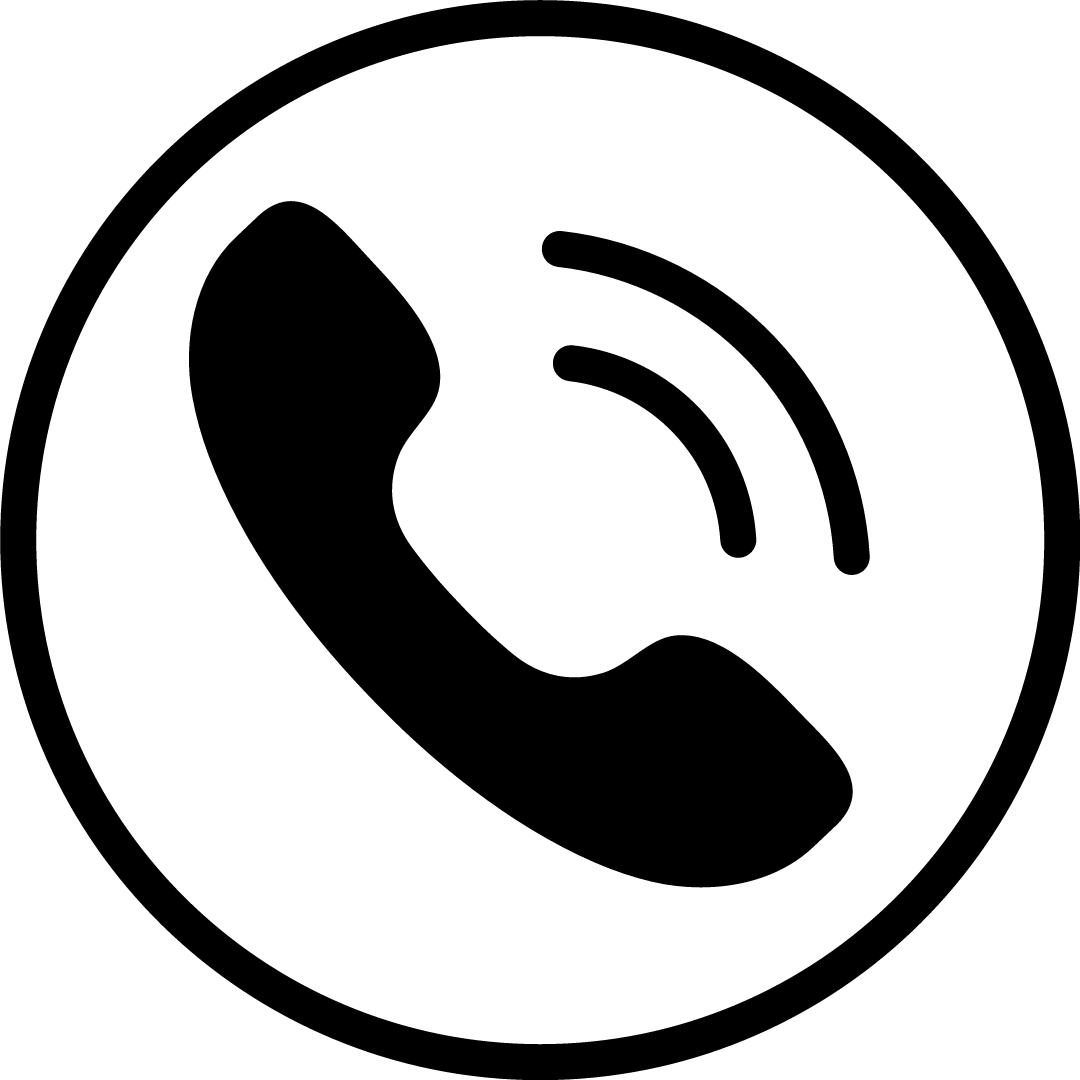 電話
電話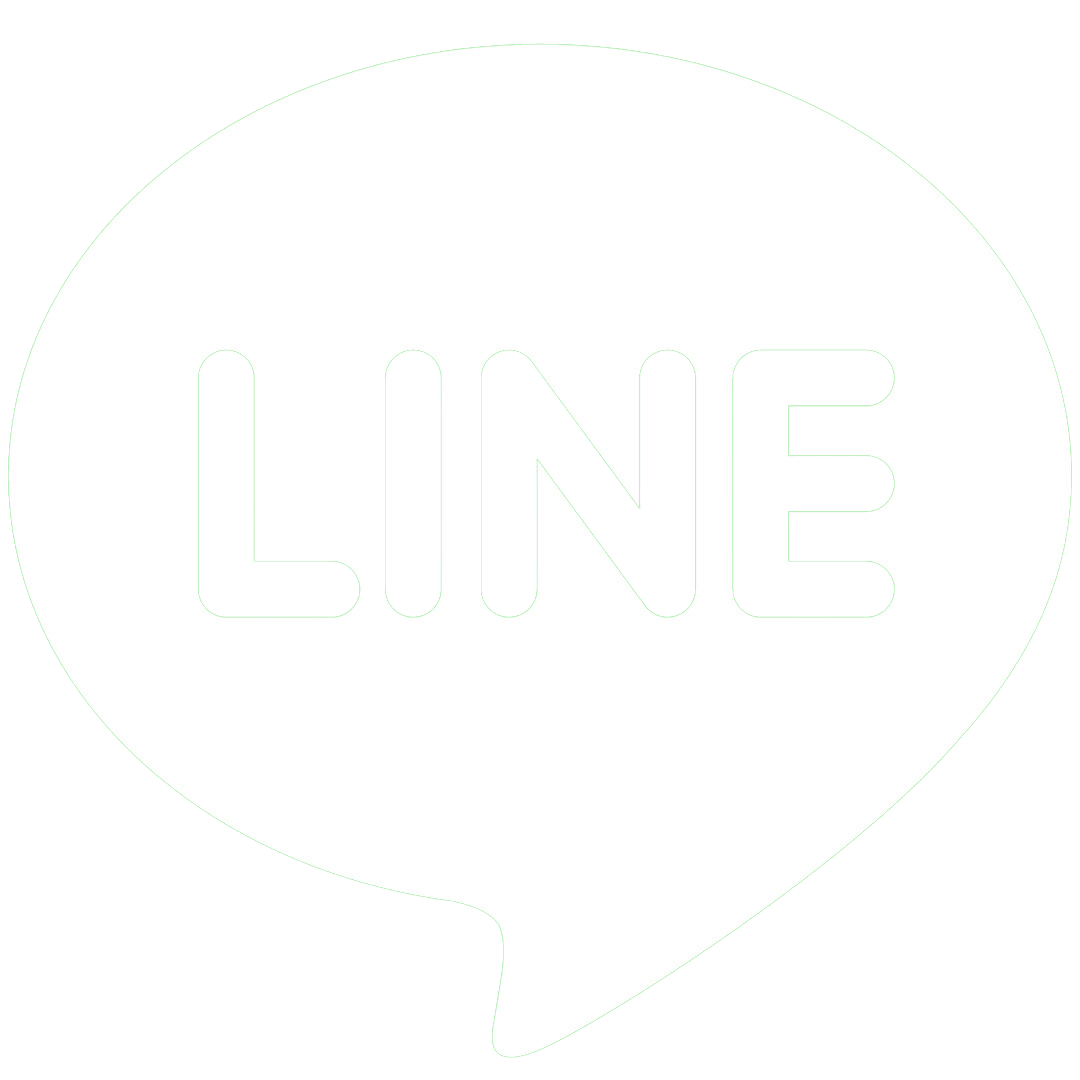 ライン予約はこちら
ライン予約はこちら