獣医師コラム一覧
-
- 2025/06/30
- 犬や猫の留守番中に起...
-
- 2025/06/30
- 犬や猫の車酔いを防ぐ...
-
- 2025/06/30
- 猫にも高血圧があるっ...
-
- 2025/06/30
- 猫喘息について|咳や...
-
- 2025/06/12
- 猫の角膜潰瘍について...
-
- 2025/06/12
- 犬や猫のお薬の飲ませ...
-
- 2025/06/12
- 犬と猫の食物アレルギ...
-
- 2025/06/12
- 犬や猫の健康管理の基...
-
- 2025/04/15
- 犬や猫の血液検査で分...
-
- 2025/04/15
- 犬や猫の爪切りについ...
獣医師コラム
犬と猫の健康チェックについて|年齢別のポイントと予防法を獣医師が徹底解説
倉敷市、岡山市、総社市、浅口市、玉野市、早島町の皆さんこんにちは。
岡山県倉敷市の倉敷動物愛護病院の院長垣野です。
近年、病気の予防や早期発見・早期治療が進んでいることから、犬や猫の平均寿命は年々伸びてきています。
そのため、愛犬や愛猫が元気で長生きするためには、年齢に応じた適切な健康管理を行うことがとても大切です。
特に、犬や猫の7歳は人間の50歳程度に相当するといわれており、この頃から健康管理をより一層徹底する必要があります。シニア期に入る前後のこの時期は、生活習慣や体調に気を配り、病気の予防や早期対応を意識することが重要です。
今回は、犬や猫の年齢別に押さえておきたい健康チェックポイントや、獣医師による健診の必要性について詳しく解説します。

■目次
1.子犬・子猫期(~1歳)の健康チェック
2.成犬・成猫期(1~7歳)の健康チェック
3.シニア期(8歳~)の健康チェック
4.まとめ
子犬・子猫期(~1歳)の健康チェック
子犬や子猫は、成長スピードが最も早い時期です。一方で免疫力がまだ低く、病気にかかりやすいデリケートな時期でもあります。この時期に健康管理をしっかり行うことで、健やかな成長をサポートできます。以下のポイントを参考に、日々のチェックを行いましょう。
<体重の確認>
生後8〜10か月くらいまでは、体重が順調に右肩上がりで増えていくのが一般的です。体重が増えない場合、食事量が足りていない可能性や病気の兆候が考えられるため、毎日体重を測る習慣をつけましょう。
また、体重や月齢に合わせて食事量をこまめに調整することが大切です。
<予防接種・寄生虫予防>
子犬や子猫は免疫力が低いため、感染症にかかりやすい状態です。混合ワクチンの予防接種や、フィラリア予防、ノミ・マダニ予防を計画的に行いましょう。
特に予防接種は初年度に複数回接種が必要です。かかりつけ医と相談しながらスケジュールを立てて、忘れずに実施してください。
<食欲・便の状態を確認>
体調不良は、食欲や便の状態に現れることが多いです。子犬や子猫は体が小さいため、食欲不振や下痢が続くと命に関わる場合があります。毎日欠かさずにチェックし、異常があれば早めに対応しましょう。
<異常行動のサインを見逃さない>
落ち着かずウロウロする、食糞をするなどの行動が見られた場合、病気の可能性が考えられます。いつもと違う行動をしたら注意深く観察し、必要に応じて獣医師に相談してください。
<運動量の確認>
成長に伴い必要な運動量も増えていきます。生後3か月の子犬や子猫であれば1回10分程度の散歩を目安にし、月齢が1か月進むごとに5分ずつ時間を増やしましょう。最終的には1回20〜30分程度になるように調整するとよいでしょう。
子犬や子猫は、ちょっとしたことで体調を崩しやすく、状態が悪化するのも早いです。特に生後6か月くらいまでは、毎月健康診断を受けることで安心して成長を見守ることができます。
成犬・成猫期(1~7歳)の健康チェック
成犬・成猫期は、成長が落ち着き体が丈夫になる一方で、マイナートラブルが増える時期でもあります。日々の健康管理や定期健診を行うことで、病気を未然に防ぎましょう。
<体重管理>
おやつの与えすぎや運動不足は肥満の原因になります。愛犬や愛猫を上から見てくびれがない場合や、体に触ったときにあばら骨が確認できない場合は肥満のサインです。適切な食事管理と運動を心がけましょう。
<歯の状態>
3歳以上の犬や猫の80%が歯周病にかかるといわれています。歯の表面に汚れや歯石がついていないか、日頃からチェックしましょう。歯磨きの習慣も取り入れるとよいでしょう。
<皮膚・被毛の状態>
皮膚病が発生する犬や猫も多いためグルーミングやトリミングを定期的に行い、以下のような症状がないか確認しましょう。
・皮膚に赤みやできものはないか
・フケが出ていないか
・被毛にツヤはあるか
・脱毛はないか
<運動量と体力>
成犬や成猫は体力が余ると、問題行動(無駄吠えや粗相、噛み癖など)やストレスにつながることがあります。散歩や遊びで適度な運動量を確保し、エネルギーをしっかり発散させましょう。
<食欲・排泄の状態>
便や尿、食欲の状態の変化は体調不良のサインである可能性があります。日常的に観察を行い、いつもと違う様子があれば注意してください。
<病院での健康チェック>
・定期健診
1年に1回の定期健診は、病気の早期発見に欠かせません。特に血液検査は、内臓の病気を早期に見つけるため、必ず受けるようにしましょう。
・歯科検診
犬や猫は歯垢が短期間で歯石へ変わり、一度ついた歯石は自然に取れません。放置すると歯周病につながるため、3〜6か月に1回を目安に歯科検診を受けましょう。
・予防接種
年に1回の追加接種を行うことで、感染症のリスクを低減できます。室内飼いであっても、飼い主様の靴や洋服を介して病原体が持ち込まれる可能性があるため、忘れずに接種しましょう。
・寄生虫予防
フィラリア予防薬:5月~12月にかけて投与を継続
ノミ・マダニ予防薬:通年の継続投与
1回の投与を忘れると感染するリスクが高まります。獣医師の指示に従いながら、確実に実施しましょう。
シニア期(8歳~)の健康チェック
シニア期に入ると、病気のリスクが大幅に高まります。この時期は、進行性の病気も増えるため、早期発見と適切な治療が予後を大きく左右します。
以下のポイントを参考に、日々の健康チェックを行いましょう。
<行動の変化>
加齢に伴い、元気が少しずつなくなり、寝ている時間が増えるのは自然なことです。ただし、以下のような行動が見られる場合は病気の可能性もあります。
・ぐったりしている
・呼吸が荒い
・落ち着きがない
<食欲・飲水量の変化>
シニア期になると、食欲や水を飲む量が減ることがあります。これは加齢による自然な変化の場合もありますが、次のような様子が見られる場合は病気が隠れている可能性があります。
・ごはんを食べづらそうにしている
・水を自分では飲みに行かないが、近くまで運ぶと飲む
単なる老化かどうかを見極めるために日頃からしっかり観察し、異常を感じたら早めに獣医師に相談しましょう。
<関節の状態>
シニア期は関節炎が起こりやすくなります。
寝起き後の立ち上がりが遅い、段差の上り下りやジャンプをしなくなった、寝ている時間が増えたなどの症状が見られた場合は、関節の異常を疑いましょう。
<体重の変化>
シニア期の前半では代謝が落ちることで体重が増えることがありますが、加齢が進むと筋肉量が減り、体重が減少していきます。
・体重が増えすぎる場合:肥満による病気のリスクが高まるため、運動量や食事量を調整しましょう。
・体重が減りすぎる場合:筋肉量の減少以外に病気の可能性が考えられるため、注意深く観察してください。
<認知機能の変化>
犬や猫も加齢とともに認知機能が低下することがあります。以下のような行動が見られる場合、認知症の可能性があります。
・同じ場所をぐるぐる回る
・狭いところに入りたがる
・昼夜が逆転する
・夜鳴きをする
・粗相の頻度が増える
獣医師による健康診断の重要性
犬や猫は本能的に痛みや病気を隠す習性があり、ギリギリまで我慢してしまうことがあります。そのため、飼い主様が異変に気づいたときには病気が進行しているケースも少なくありません。また、初期症状が出ない病気も多く存在します。
こうした病気を早期に発見するために、定期的な健康診断は欠かせません。診断を通じて、表面からは分からない異常を見つけることができる可能性があります。定期健診を受けることで、愛犬や愛猫が健康で長く元気に過ごせるようサポートできます。
<健康診断の頻度>
・成犬、成猫期(1~7歳):年に1回を目安に定期健診を受けましょう。
・シニア期(8歳~):半年に1回のペースで健診を受けるのがおすすめです。
<主な検査項目>
健康診断の内容は年齢や病院によって異なりますが、以下のような検査を行うことで、多くの病気を早期に発見できる可能性があります。
・血液検査:内臓機能や感染症の有無を調べる
・尿検査:腎臓や尿路の状態を確認する
・糞便検査:寄生虫や消化器の状態をチェックする
・画像検査(レントゲンや超音波):骨や内臓の異常を調べる
特にシニア期には病気のリスクが高まるため、こうした検査を積極的に取り入れることで、愛犬や愛猫の健康を守る手助けになります。
まとめ
犬や猫は年齢によってかかりやすい病気が異なるため、それぞれのライフステージに合わせた健康チェックが必要です。
獣医師による定期健診はもちろん大切ですが、飼い主様が日頃から愛犬や愛猫の些細な変化に気づくことで、病気を早期に発見・治療できるケースも少なくありません。
大切な家族である愛犬や愛猫の健康を守るために、毎日の観察を心がけるとともに、気になることがあれば早めに動物病院に相談するようにしましょう。
■関連する記事はこちらで解説しています
・犬や猫の病気のサインを見逃さないために|気をつけたい症状や行動変化
岡山県倉敷市にある「倉敷動物愛護病院」
ペットと飼い主様にとって最善の診療を行うことを心がけております。
一般診療はこちらから
獣医師コラム一覧
-
- 2025/06/30
- 犬や猫の留守番中に起こるトラブ...
-
- 2025/06/30
- 犬や猫の車酔いを防ぐには?移動...
-
- 2025/06/30
- 猫にも高血圧があるって知ってい...
-
- 2025/06/30
- 猫喘息について|咳や呼吸の異変...
-
- 2025/06/12
- 猫の角膜潰瘍について|目の充血...
-
- 2025/06/12
- 犬や猫のお薬の飲ませ方について...
-
- 2025/06/12
- 犬と猫の食物アレルギーについて...
-
- 2025/06/12
- 犬や猫の健康管理の基本ポイント...
-
- 2025/04/15
- 犬や猫の血液検査で分かることに...
-
- 2025/04/15
- 犬や猫の爪切りについて|安全に...
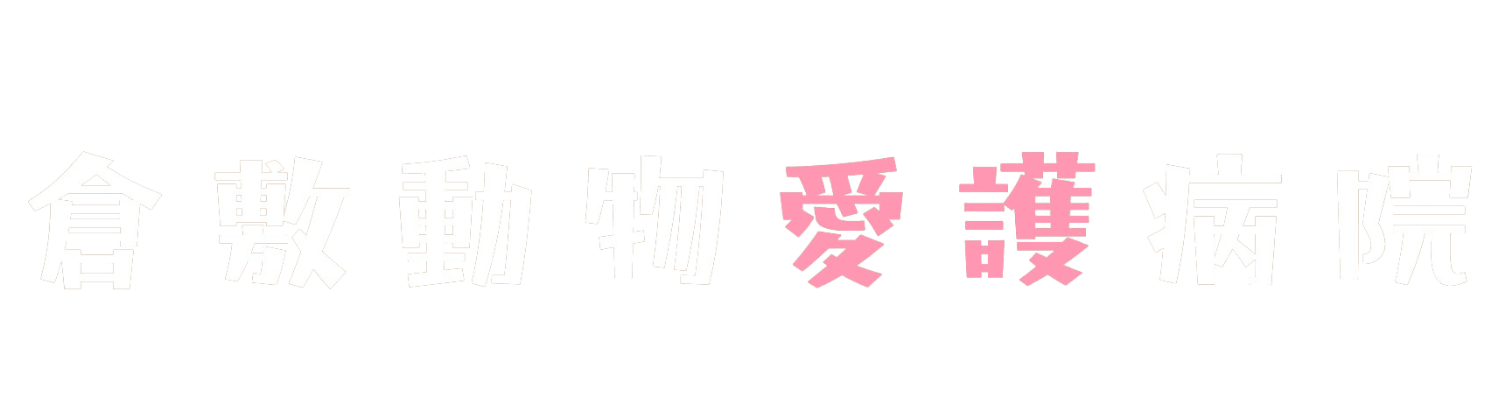
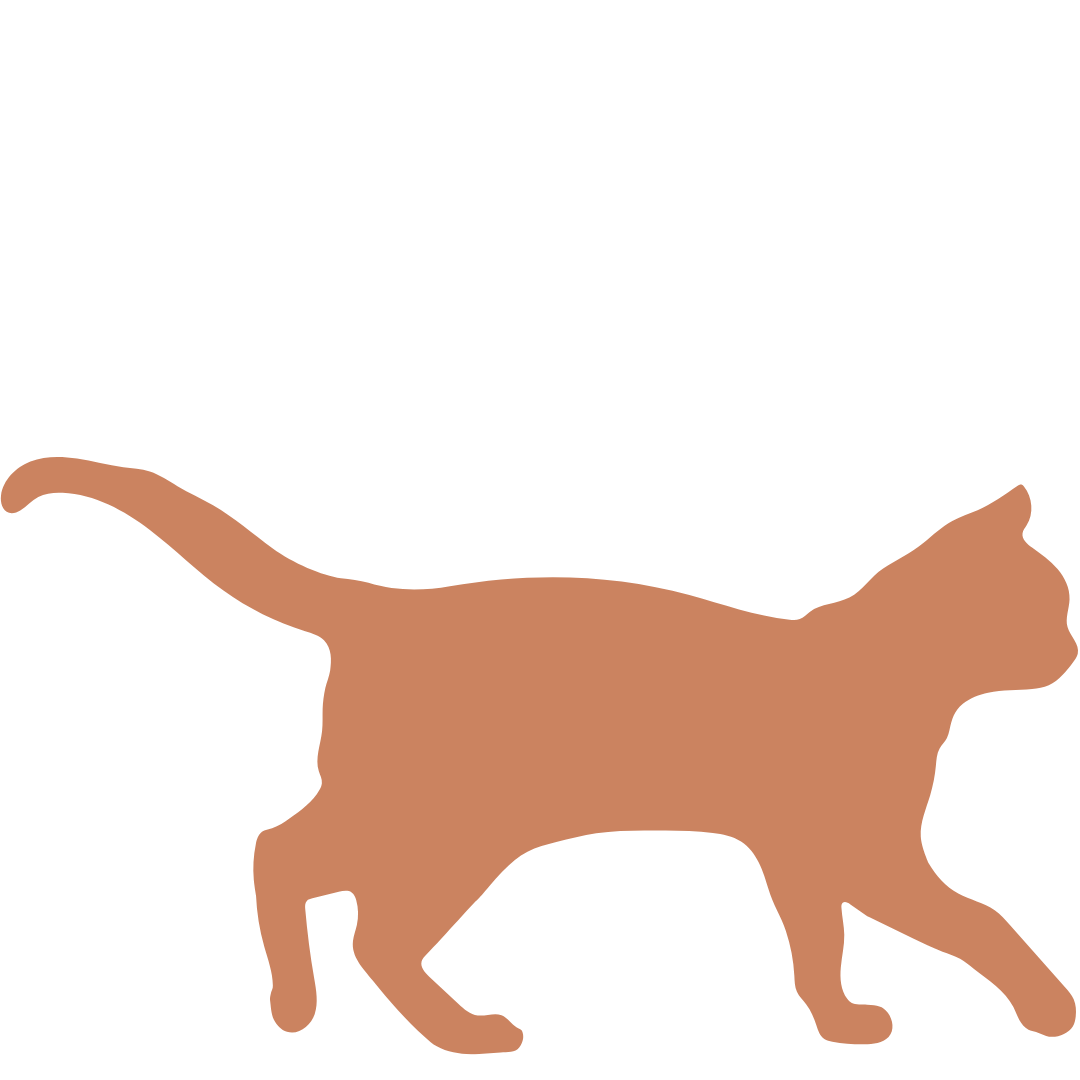
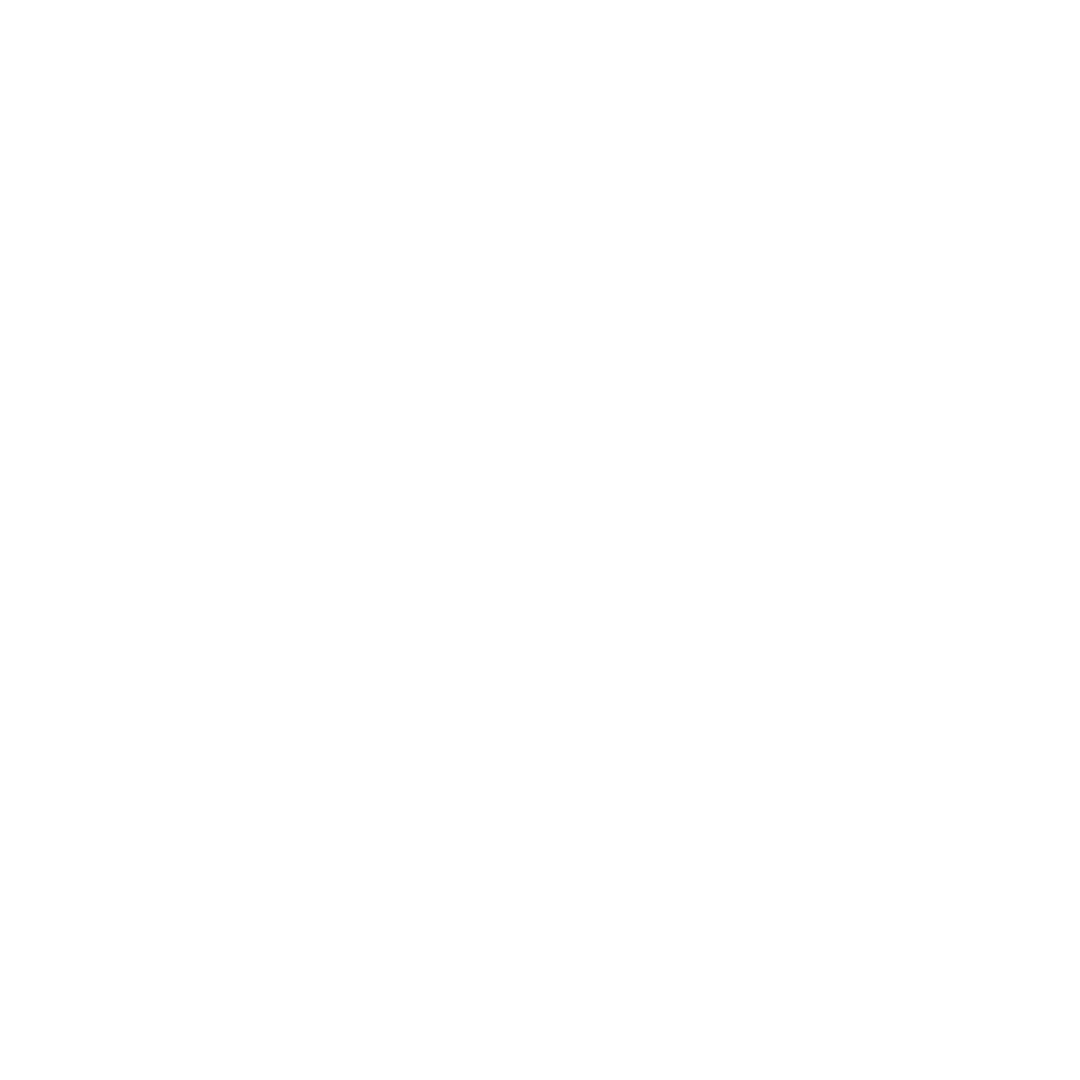
 インスタグラム
インスタグラム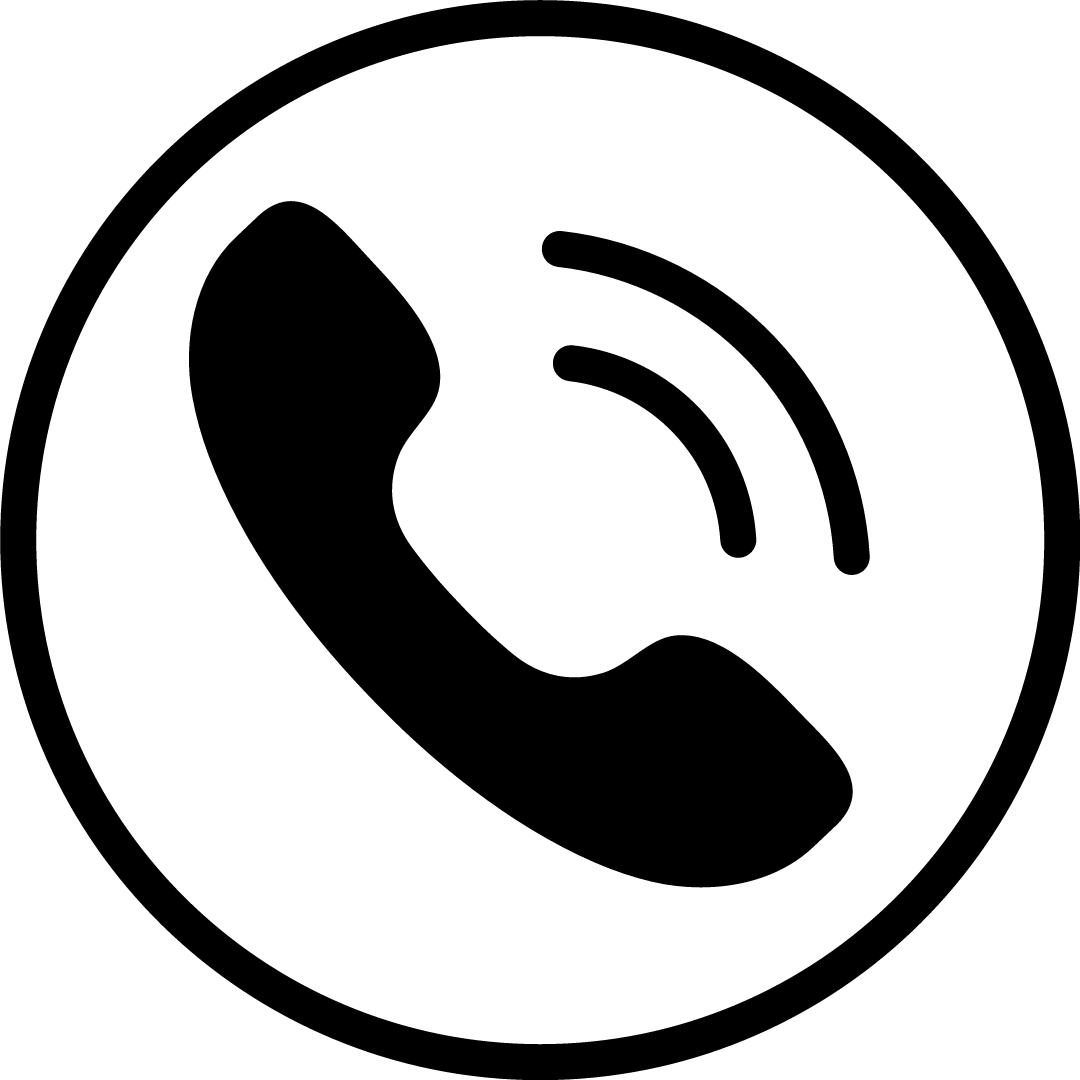 電話
電話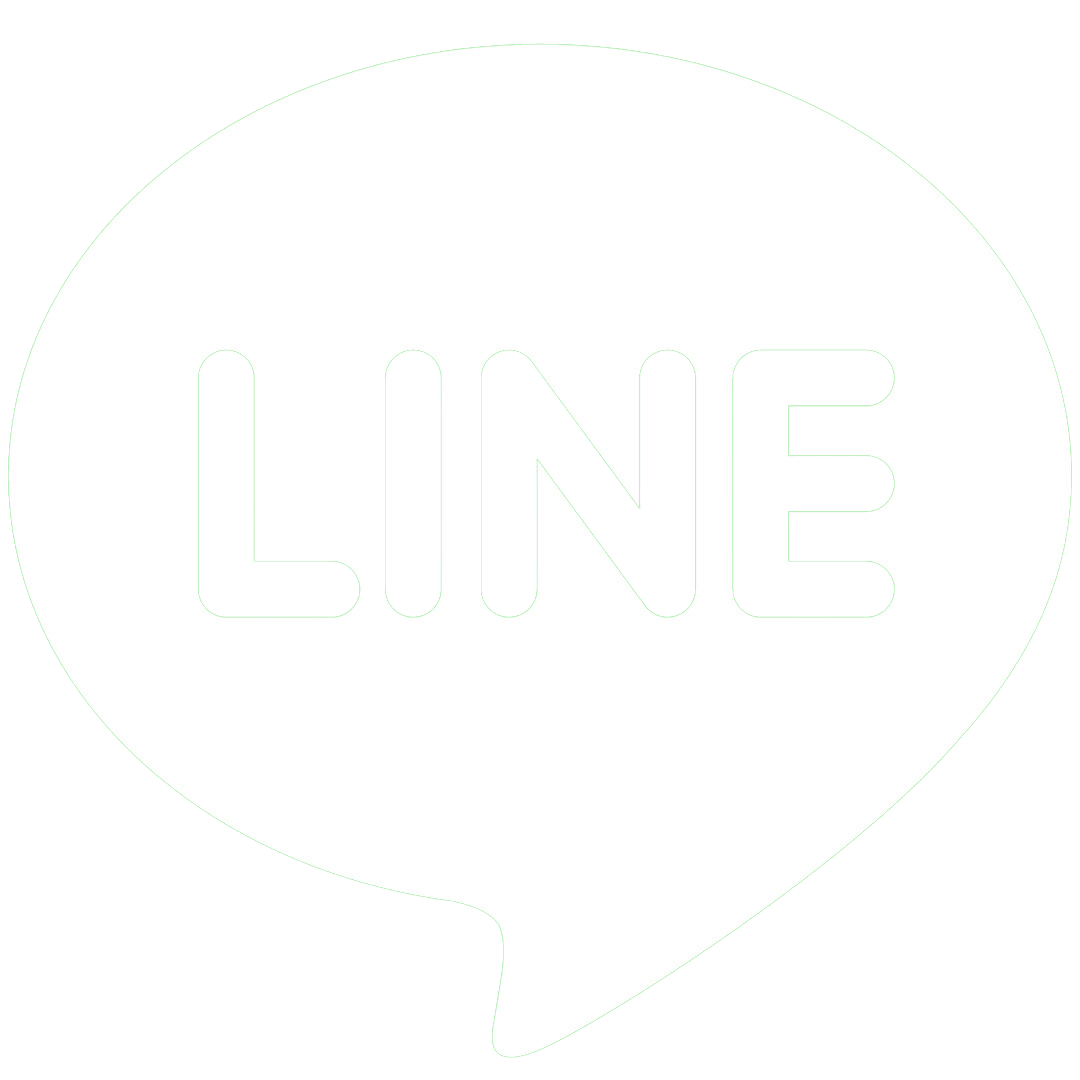 ライン予約はこちら
ライン予約はこちら