獣医師コラム一覧
-
- 2025/12/16
- 犬や猫の噛み癖の理由...
-
- 2025/12/16
- 犬猫のよだれが多いの...
-
- 2025/12/09
- 犬の皮膚がカサカサ?...
-
- 2025/12/02
- 犬と猫の頻尿・血尿・...
-
- 2025/10/06
- 猫が毛玉を吐くのは病...
-
- 2025/10/06
- ペットロスの向き合い...
-
- 2025/10/06
- 愛犬の歩き方がおかし...
-
- 2025/10/06
- シニア犬、シニア猫(...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の成長に合...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の「社会化...
獣医師コラム
犬や猫が嘔吐した際の受診のタイミングについて|症状の違いと注意すべきポイント
倉敷市、岡山市、総社市、浅口市、玉野市、早島町の皆さんこんにちは。
岡山県倉敷市の倉敷動物愛護病院の院長垣野です。
愛犬や愛猫が突然嘔吐すると、驚いてしまう飼い主様も多いのではないでしょうか。
犬や猫の嘔吐は決して珍しいことではなく、一時的な胃腸の不調で起こることもあれば、重大な病気のサインであることもあります。
そのため「いつものことだから様子を見ても大丈夫?」と考えることもあれば、「すぐに病院に行くべき?」と迷うこともあるかもしれません。
今回は、嘔吐の原因や危険な嘔吐の見分け方、適切な対応について詳しく解説します。

■目次
1.嘔吐の原因
2.嘔吐の原因として考えられる病気
3.病院に行く判断基準
4.診断方法
5.治療方法
6.嘔吐を防ぐための予防方法と自宅でのケア
7.まとめ
嘔吐の原因
犬や猫の嘔吐は、大きく分けて「消化器が原因の嘔吐」と「その他の疾患が原因の嘔吐」の2つに分類されます。
<消化器が原因の嘔吐>
消化器の不調による嘔吐は比較的軽度なことが多く、以下のような場合は一時的なものであることが多いため、しばらく様子を見てもよいでしょう。
・食事を早食いした後に吐く
・空腹時に黄色い液体(胆汁)を吐く
・食べすぎによる消化不良で吐く
しかし、嘔吐が何度も続く場合や、食後すぐに吐いてしまう状態が続く場合は注意が必要です。
また、以下のような状況でも嘔吐が見られることがあります。
・急に新しいフードに切り替えた
・食べ慣れないものを食べた
・ストレスや環境の変化による胃腸トラブル
これらのケースでは、フードを一時的に消化の良いものに変える、少量ずつ与えるなどの工夫で改善することが多いです。しかし、嘔吐が長引いたり、他の症状(元気がない・下痢・食欲不振など)が見られたりする場合は、病院での相談を検討してください。
<その他の疾患が原因の嘔吐>
嘔吐は消化器の不調だけでなく、さまざまな病気のサインとして現れることもあります。
特に、食欲が低下している場合は何らかの病気が関与している可能性があります。
また、嘔吐に加えて、元気がない・下痢・発熱などの症状が見られる場合は、以下のような病気の可能性も考えられます。
・腎臓病や肝臓病
・中毒(チョコレート、ネギ類、薬物誤飲など)
・熱中症
嘔吐の原因として考えられる病気
嘔吐の原因は多岐にわたり、消化器系の問題だけでなく、他の臓器の疾患や年齢による違いも考えられます。以下に、嘔吐の主な原因をまとめました。
<消化器に原因がある場合>
嘔吐の多くは、胃や腸などの消化器に問題があることが原因です。代表的な疾患をいくつかご紹介します。
・胃腸炎
ウイルスや細菌の感染、食べ物の変化、ストレスなどが原因で起こります。嘔吐のほかに、下痢や食欲不振を伴うこともあります。
軽い場合は様子を見ることもできますが、症状が長引く場合や悪化する場合は、早めに動物病院を受診しましょう。
・異物誤飲
犬や猫は、おもちゃや布、ビニールなどを誤って飲み込んでしまうことがあります。異物が胃や腸に詰まると繰り返し嘔吐をし、元気がなくなったり食欲が落ちたりすることがあります。放っておくと腸閉塞を引き起こし、手術が必要になることもあるため、注意が必要です。
<消化器以外の臓器が原因の場合>
嘔吐は、胃や腸だけでなく、他の臓器の異常によっても引き起こされることがあります。
・腎臓の病気
慢性腎臓病や急性腎不全になると、体内の老廃物がうまく排出されず、嘔吐や食欲不振の症状が現れます。特に高齢の猫では発症しやすいため、定期的な健康チェックを心がけましょう。
・ 肝臓の病気
肝炎や肝不全が進行すると、解毒機能が低下し、嘔吐のほかに黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)や食欲不振の症状が出ることがあります。重症化すると命に関わるため、早期発見・早期治療が大切です。
<年齢による違い>
犬や猫の年齢によって、嘔吐の原因が異なることがあります。
・若い犬や猫
子犬や子猫では、誤飲や感染症による嘔吐が多く見られます。体力が少ないため、短期間の嘔吐でも脱水しやすく、注意が必要です。
・成犬や成猫
食事内容の変化やストレスによる一時的な胃腸炎が原因で嘔吐することがあります。ただし、嘔吐が続く場合は、消化器の病気や内臓の異常が隠れている可能性も考えられます。
・高齢の犬や猫
年をとると、腎臓や肝臓の病気が原因で嘔吐することが多くなります。また、食欲不振や体重減少を伴うことも多いため、定期的な健康診断を受け、早めに異常を発見できるようにすることが大切です。
病院に行く判断基準
愛犬や愛猫が嘔吐したとき、「様子を見ても大丈夫か」「すぐに病院に行くべきか」を見極めることが大切です。
<早急に受診が必要な症状>
以下のような症状がある場合は、緊急性が高いため、できるだけ早く動物病院へ連絡し、受診しましょう。
・食欲低下を伴う嘔吐
何も食べずに吐いてしまう、または食べた直後に吐いてしまう。水も飲めずに嘔吐する。
・高齢の犬や猫の嘔吐
高齢の犬や猫は、腎臓病や肝臓病などの慢性疾患や腫瘍の可能性があるため、嘔吐が続く場合は早めに診察を受けましょう。
・繰り返し嘔吐する
1日に何度も吐く、または数日間にわたり嘔吐を繰り返す。
・元気がない、ぐったりしている
嘔吐とともにぐったりして動かず、目の輝きがなく反応も鈍い。
・血液が混じった嘔吐
吐しゃ物に赤い血が混じる(胃潰瘍や消化管出血の可能性)
<様子を見てもよい症状>
以下のような場合は、すぐに受診しなくても様子を見てもよいことが多いですが、症状が悪化する場合は病院で相談しましょう。
・食欲が維持されている
嘔吐後も普段どおりに食事や水分を摂れている場合は、一時的な不調の可能性が高いです。
・若齢で他の症状がない
子犬や子猫は消化器が未熟なため、一時的に嘔吐することがあります。
・1回だけの嘔吐
1回だけの嘔吐で、その後元気や食欲が普段通りであれば、様子を見ても問題ないことが多いです。
診断方法
動物病院ではまず問診を行い、必要に応じて詳しい検査を進めながら嘔吐の原因を特定していきます。
1.問診で確認するポイント
診察では、飼い主様から愛犬や愛猫の様子について詳しく聞き取ります。特に、以下のような情報が診断の手がかりになります。
・嘔吐が始まった時期(いつから吐くようになったか)
・嘔吐の頻度(1回だけか、何度も繰り返しているか)
・嘔吐の内容物(未消化の食べ物、血液、泡、黄色い液体など)
・食欲や元気の状態(普段と比べて変化があるか)
・他の症状があるか(下痢、発熱、腹痛など)
・誤飲の可能性(おもちゃや布などを飲み込んでいないか)
・最近の食事や生活環境の変化(新しいフードに変えた、引っ越しをしたなど)
2.身体検査
問診の後は愛犬や愛猫の体を直接診察し、嘔吐の原因を調べます。主に、次のような検査が行われます。
・体温測定(発熱の有無を確認)
・腹部の触診(腸の張りや痛み、異物がないかをチェック)
・口の中の確認(脱水症状や粘膜の異常がないか)
・心音・呼吸音のチェック(心臓や肺に異常がないかを確認)
3.血液検査
嘔吐の原因を詳しく調べ、適切な治療を行うために、血液検査を実施することがあります。
・食欲が落ちている場合の血液検査
脱水の有無・低血糖の有無・感染の兆候などを調べます。
・高齢の犬や猫の血液検査
腎臓や肝臓の機能をチェックし、慢性疾患の有無を確認します。
4.その他の検査(必要に応じて実施)
症状や診察結果によっては、さらに詳しく調べるために追加の検査を行うこともあります。
・レントゲン検査(異物の誤飲や腸閉塞の可能性を確認)
・超音波検査(消化器や内臓の状態を詳しくチェック)
・糞便検査(寄生虫や細菌感染の有無を調べる)
治療方法
嘔吐の治療は、その原因や重症度によって異なります。軽い症状であれば食事管理だけで改善することもありますが、重症の場合は点滴や投薬治療が必要になることもあります。
<点滴治療>
嘔吐が続くと、体内の水分や電解質のバランスが崩れ、脱水症状を引き起こすことがあります。特に高齢の犬や猫や、頻繁に嘔吐している場合は、点滴治療が必要になります。
<投薬治療>
嘔吐の原因に応じて、さまざまな薬を使用します。
例えば、嘔吐を抑える制吐剤や、胃の粘膜を保護する胃粘膜保護剤、細菌感染が疑われる場合の抗生物質などです。もし、寄生虫が原因で嘔吐している場合は、駆虫薬を使うこともあります。
<食事管理>
胃腸を休めるために、8〜12時間ほど絶食を行うことがあります。その後、消化の良いフードを少量ずつ与え、胃腸への負担を減らしていきます。
消化に優しい食事としては、獣医師が推奨する消化器サポートフードや、茹でた鶏肉や白身魚などが適しています。嘔吐が落ち着くまでは、脂っこい食べ物や刺激の強い食材は避けるようにしましょう。
<原因となる病気の治療>
もし嘔吐の原因が腎臓病・肝臓病・腫瘍などの病気である場合は、それに対する治療が必要になります。
嘔吐を防ぐための予防方法と自宅でのケア
嘔吐は、食事の与え方や生活環境を工夫することで予防できる場合があります。日頃から愛犬や愛猫の健康管理を意識し、適切なケアを心がけましょう。
<食事の与え方>
食事は、一度にたくさん与えるのではなく、少量を数回に分けて与えることで、胃腸への負担を減らすことができます。特に、早食いしやすい犬や猫には、食べるスピードを調整できるフードボウルを使うのもおすすめです。
また、消化の良いフードを選ぶことも大切です。急にフードを変えると胃腸に負担がかかり、嘔吐を引き起こすことがあるため、新しいフードに切り替えるときは数日かけて少しずつ混ぜながら移行 しましょう。
さらに、誤飲や食べすぎを防ぐための工夫も必要です。テーブルの上の食べ物やゴミ箱の中の残飯を誤って食べてしまわないよう、環境を整えましょう。フード管理用のボックスを活用するのもおすすめです。
<生活環境の整備>
ストレスが原因で嘔吐することもあるため、静かで落ち着ける環境を整えることが大切です。来客が多い場合や大きな音が頻繁にする場所では、犬や猫が落ち着かないこともあります。リラックスできるスペースを作ってあげましょう。
また、温度や湿度の管理も重要です。特に寒暖差が激しいと体調を崩しやすくなるため、室内の温度は一定に保つようにしましょう。
<日頃の観察ポイント>
愛犬や愛猫の健康を守るためには、日々の観察がとても大切です。
まず、食欲や排便の状態、元気の有無を毎日確認しましょう。少しの変化も早めに気づくことで、病気の早期発見につながります。
また、万が一嘔吐した場合は、嘔吐物の状態(未消化の食べ物、泡、血液の有無など)や嘔吐の頻度を確認することが重要です。嘔吐が1回だけで、その後元気にしている場合は様子を見ることもできますが、繰り返し嘔吐する、元気がない、体重が減っているなどの異変がある場合は、すぐに動物病院へ相談しましょう。
まとめ
嘔吐は、ちょっとした消化不良から重大な病気までさまざまな原因で起こります。だからこそ、普段から愛犬や愛猫の様子をよく観察し、いつもと違う変化に気づくことが大切です。
特に、嘔吐に加えて 食欲がない、元気がないといった症状が見られるときは、早めに獣医師に相談しましょう。
また、嘔吐を防ぐには、食事の管理やストレスを減らす工夫、定期的な健康診断が欠かせません。毎日のちょっとした心がけが、愛犬や愛猫の健康を守ることにつながります。
当院では嘔吐の原因を詳しく調べ、愛犬や愛猫の体調に合わせた適切な治療を行っています。気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
岡山県倉敷市にある「倉敷動物愛護病院」
ペットと飼い主様にとって最善の診療を行うことを心がけております。
一般診療はこちらから
獣医師コラム一覧
-
- 2025/12/16
- 犬や猫の噛み癖の理由や原因は?...
-
- 2025/12/16
- 犬猫のよだれが多いのは異常?正...
-
- 2025/12/09
- 犬の皮膚がカサカサ?秋冬の乾燥...
-
- 2025/12/02
- 犬と猫の頻尿・血尿・排尿困難に...
-
- 2025/10/06
- 猫が毛玉を吐くのは病気?|毛球...
-
- 2025/10/06
- ペットロスの向き合い方~飼い主...
-
- 2025/10/06
- 愛犬の歩き方がおかしい?犬の椎...
-
- 2025/10/06
- シニア犬、シニア猫(7歳以上)...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の成長に合わせた食事...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の「社会化期」にすべ...
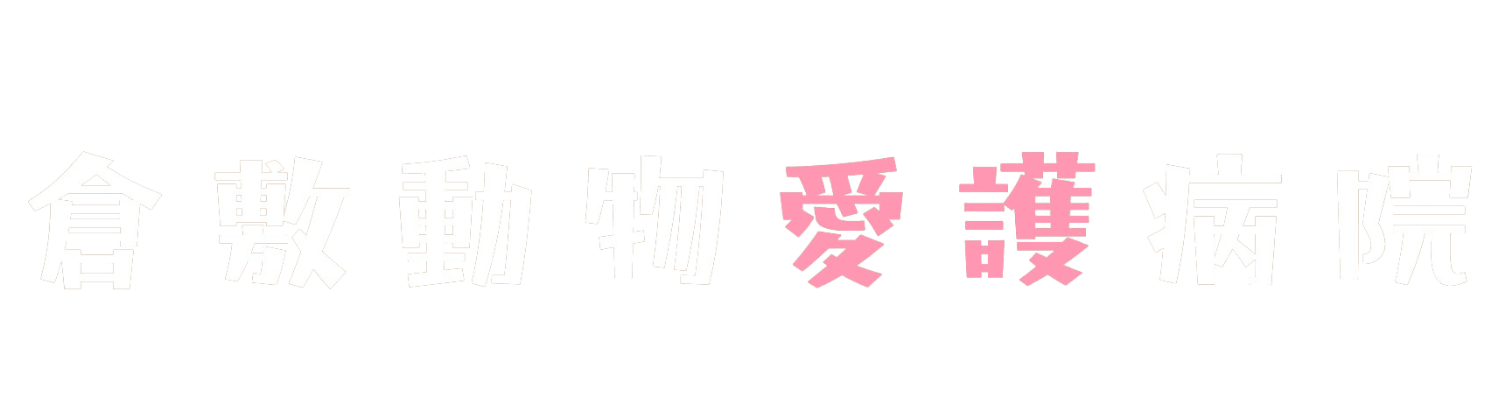
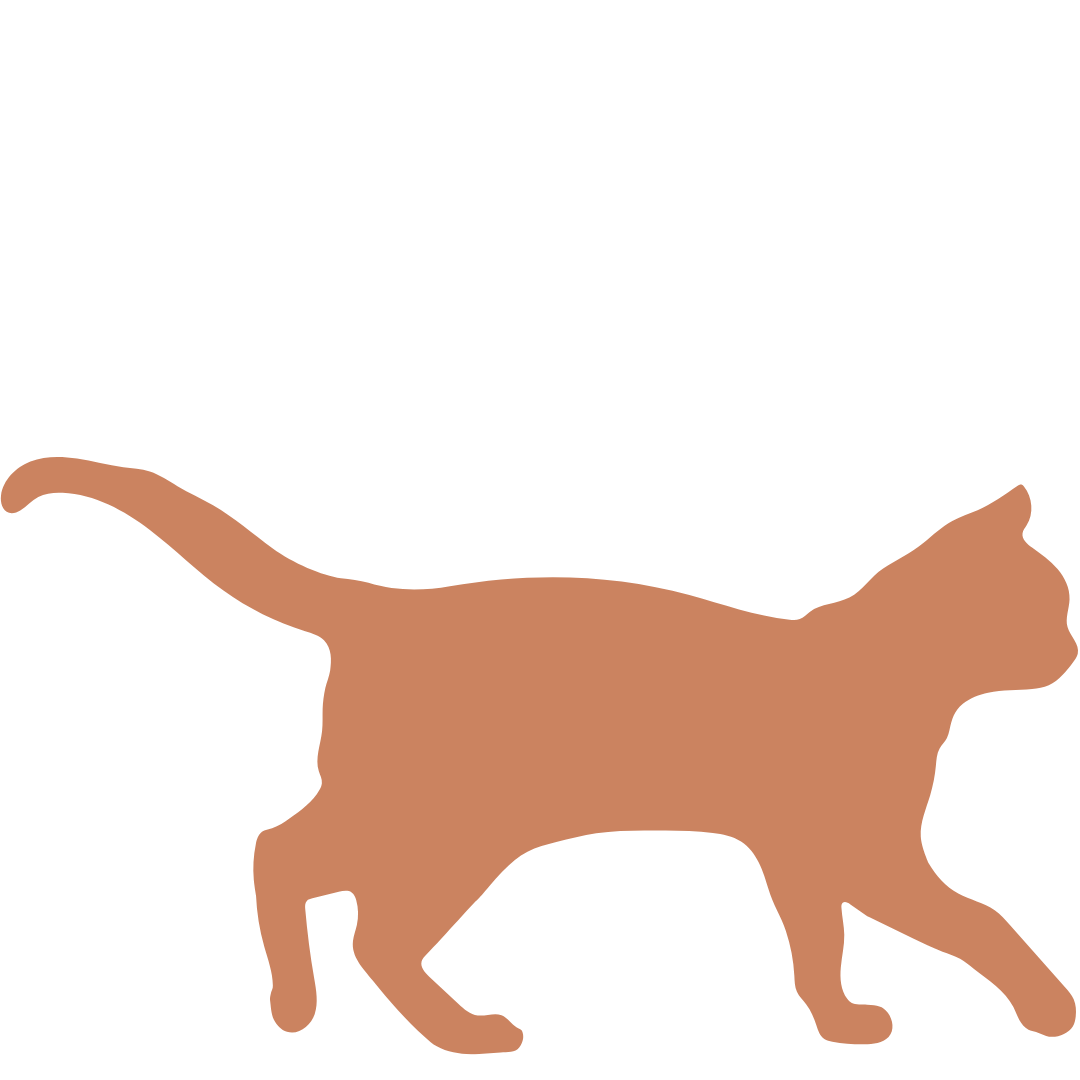
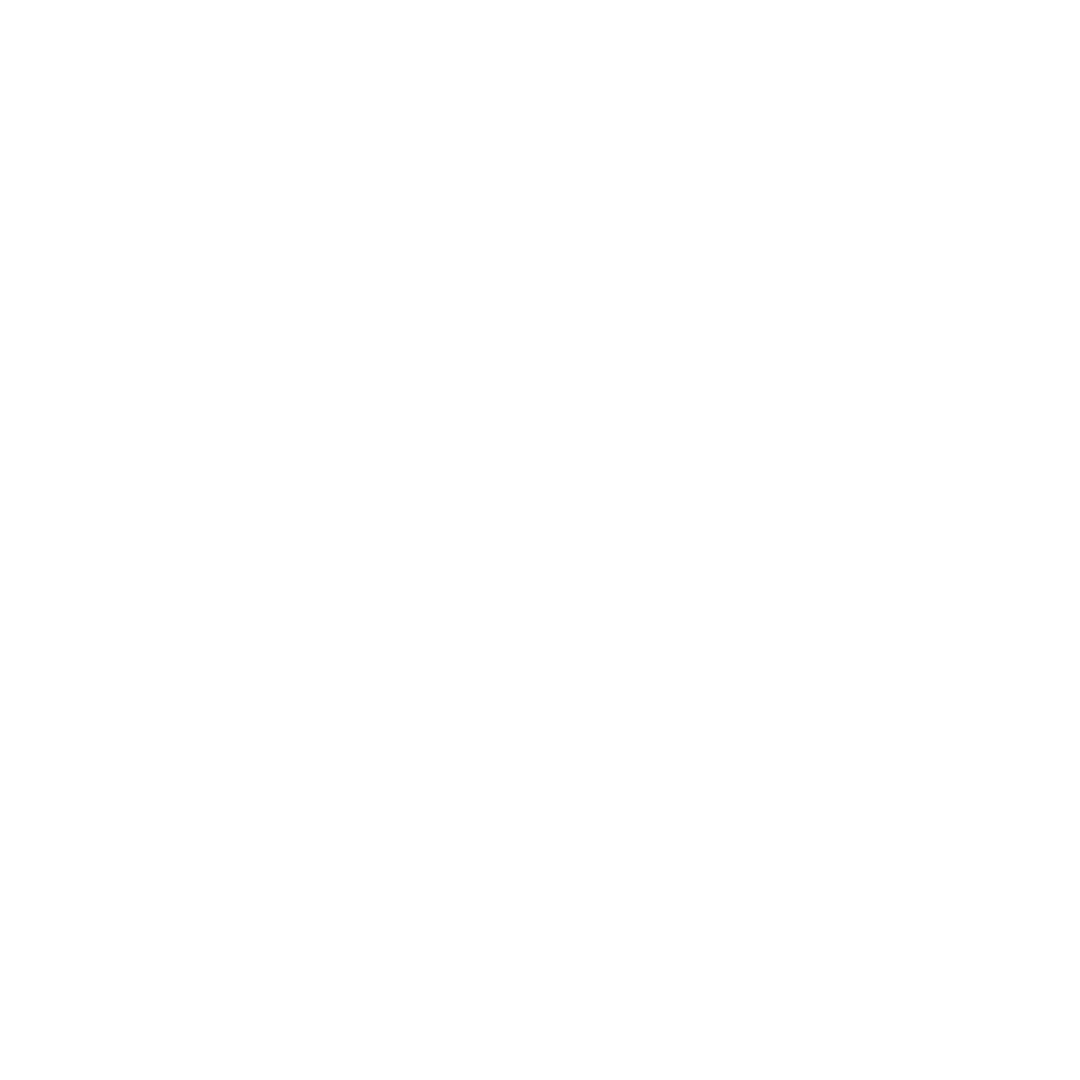
 インスタグラム
インスタグラム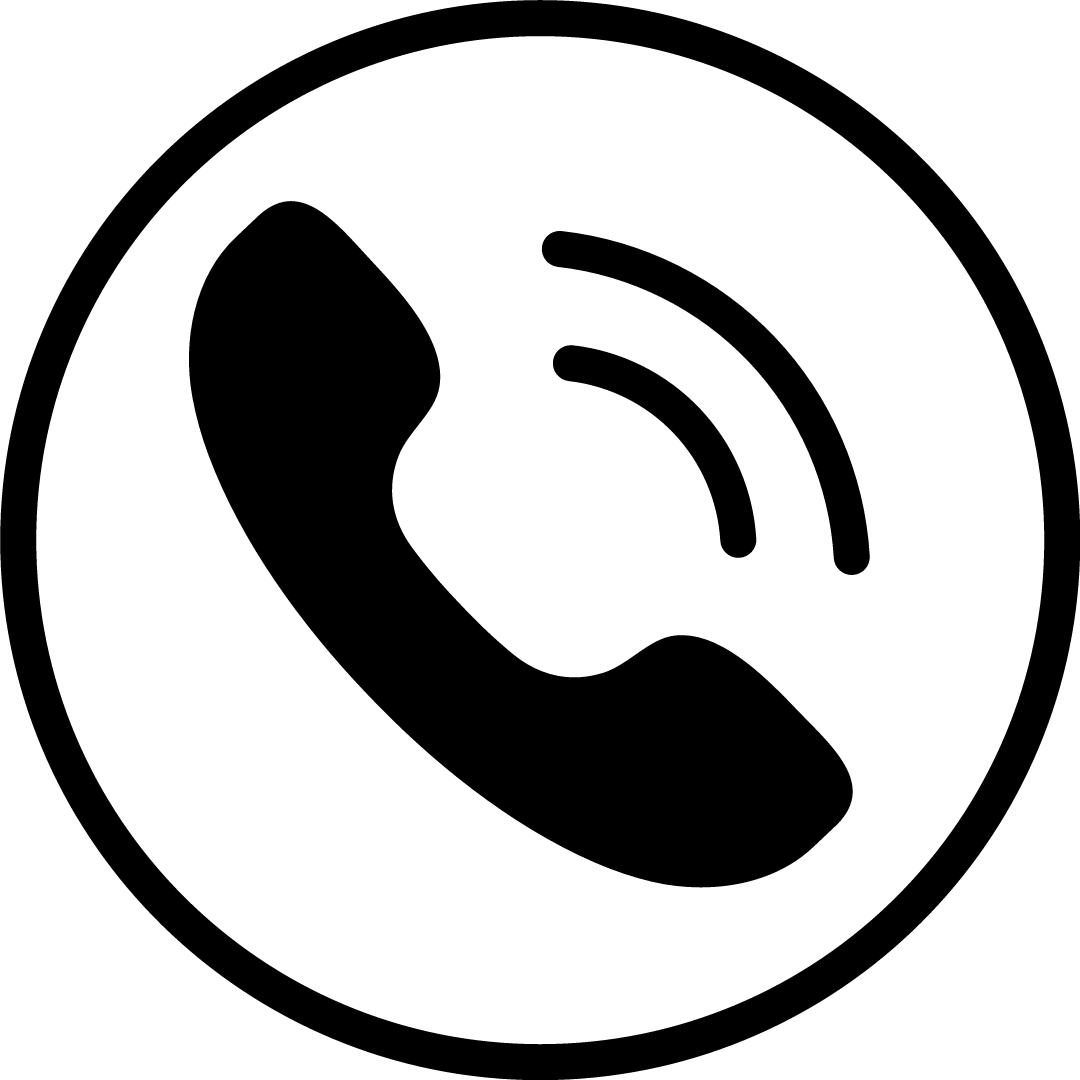 電話
電話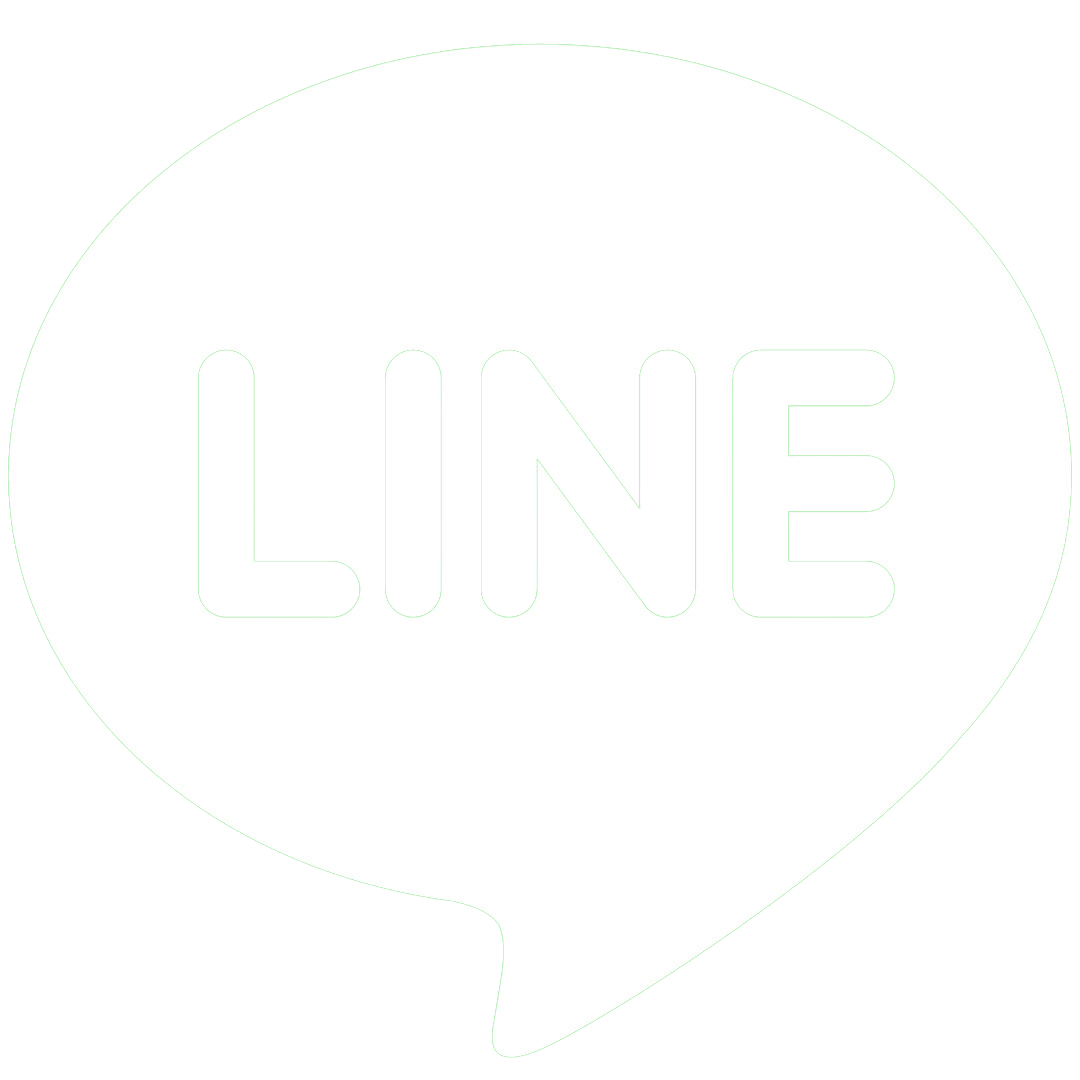 ライン予約はこちら
ライン予約はこちら