獣医師コラム一覧
-
- 2025/12/16
- 犬や猫の噛み癖の理由...
-
- 2025/12/16
- 犬猫のよだれが多いの...
-
- 2025/12/09
- 犬の皮膚がカサカサ?...
-
- 2025/12/02
- 犬と猫の頻尿・血尿・...
-
- 2025/10/06
- 猫が毛玉を吐くのは病...
-
- 2025/10/06
- ペットロスの向き合い...
-
- 2025/10/06
- 愛犬の歩き方がおかし...
-
- 2025/10/06
- シニア犬、シニア猫(...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の成長に合...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の「社会化...
獣医師コラム
猫の脱毛の原因について|症状別に考えられる原因を獣医師が解説
倉敷市、岡山市、総社市、浅口市、玉野市、早島町の皆さんこんにちは。
岡山県倉敷市の倉敷動物愛護病院の院長垣野です。
愛猫の毛がいつもより薄くなっている、部分的に毛が抜けて地肌が見えるなど、「脱毛」の症状に気づくと心配になりますよね。
猫の美しい被毛は健康状態を映し出すバロメーターとも言われており、脱毛が見られる場合には、体の内側や外側に何らかの異常が隠れている可能性も考えられます。
今回は、猫の脱毛の主な原因や症状の見分け方、治療法について詳しく解説します。

■目次
1.猫の脱毛の主な原因
2.症状の見分け方
3.診断方法
4.治療方法
5.自宅でできるケア
6.予防と対策
7.まとめ
猫の脱毛の主な原因
猫の脱毛にはさまざまな原因が考えられます。それぞれの特徴や症状について詳しく解説します。
・季節の変化による脱毛
猫は季節の変わり目に換毛期を迎えます。特に春や秋には古い毛が抜け、新しい毛に生え変わるため、一時的に多くの毛が抜けることがありますが、これは自然な生理現象ですので特に心配する必要はありません。
ただし、全身ではなく一部の毛だけが抜けている場合や、皮膚に赤み、かゆみ、フケなどの異常が見られる場合は、換毛ではなく病気の可能性も考えられます。
・アレルギー性皮膚炎
アレルギー性皮膚炎は、ハウスダストや花粉、カビ、特定の食物など、さまざまなアレルゲンに対して皮膚が過敏に反応することで発症します。この疾患では強いかゆみが伴い、猫が頻繁に舐めたり掻いたりすることで、脱毛や皮膚炎が進行することがあります。
特に、顔や耳、四肢、腹部といった部位に症状が現れやすいのが特徴です。
・ストレスによる過剰な毛づくろい
猫は非常に繊細な動物で、環境の変化や精神的なストレスに敏感です。ストレスを感じると、気持ちを落ち着かせるために過剰な毛づくろい(グルーミング)を行うことがあります。これが続くと毛が抜けてしまい、脱毛の原因となります。
新しい家族の迎え入れ、引っ越しや模様替え、飼い主様の生活リズムの変化などがきっかけになることが多いです。
脱毛は舐めやすいお腹や内股、四肢といった部位に現れることが多く、ストレスの要因を取り除くことで改善が期待できます。
・その他の皮膚疾患
皮膚真菌症(カビ)や寄生虫(ノミ、ダニ、疥癬など)による皮膚炎も脱毛の原因となります。これらの皮膚疾患では強いかゆみや炎症が起こり、猫が掻いたり舐めたりすることで症状が悪化することがあります。
皮膚に赤みやかさぶた、フケが見られる場合や、円形の脱毛が現れることが特徴です。
・内臓疾患に関連する脱毛
甲状腺機能亢進症や腎臓病などの内臓疾患が原因で脱毛が起こることもあります。この場合、脱毛だけでなく、元気がなくなったり食欲が低下したりといった全身症状が見られることが多いです。また、脱毛が左右対称に現れることもあります。
症状の見分け方
愛猫に脱毛が見られたときは、以下のポイントを確認してみましょう。
・正常な換毛との違い
季節性の換毛は全体的に均一に毛が抜けるのが特徴で、皮膚の状態は健康的です。これに対して、特定の部位だけ毛が抜けていたり、皮膚に赤みやかさぶたが見られたりする場合は、何らかの異常が隠れている可能性があります。
・脱毛の形状や範囲
脱毛の形状や広がり方も重要なポイントです。例えば、脱毛部分が円形の場合は真菌感染(皮膚糸状菌症)が疑われます。不規則な形の脱毛であれば、ストレスや外傷が原因である可能性があります。
・皮膚の状態をチェック
脱毛している部分の皮膚に赤み、かゆみ、湿疹、かさぶた、フケがある場合は、アレルギー反応や感染症の兆候かもしれません。
・かゆみがあるかどうか
猫が頻繁に掻いたり舐めたりしている場合、かゆみを伴う皮膚疾患が原因であることが多いです。
診断方法
愛猫の脱毛が気になる場合、まずは動物病院で診察を受けることが大切です。脱毛の原因はさまざまで、正確な診断が適切な治療につながります。
診察では、皮膚の状態や脱毛している部位を詳しく確認し、必要に応じて以下のような検査を行います。
・皮膚の検査:ダニや真菌(皮膚糸状菌症)の有無を調べるため、皮膚の一部を採取して顕微鏡で確認します。
・血液検査:内臓疾患やホルモン異常が原因の場合もあるため、血液検査で体全体の健康状態をチェックします。
・アレルギー検査:食物や環境中の物質に対するアレルギーが疑われる場合、アレルゲンを特定するための検査を行います。
治療方法
診断結果に応じて、以下のような薬が使用されることがあります。
<ステロイド剤>
アレルギー性皮膚炎や強いかゆみを抑えるために使用されることが多い薬です。ステロイド剤は短期的な使用が基本ですが、副作用のリスクもあるため、獣医師の指示に従い慎重に使用することが大切です。
<抗生剤>
細菌感染が確認された場合には抗生剤が処方されます。感染の程度によっては、一定期間継続して使用する必要があるため、獣医師の指示を必ず守りましょう。
<抗真菌剤>
皮膚真菌症(皮膚糸状菌症)が原因である場合、抗真菌剤の外用薬や内服薬が使われることがあります。治療と並行して、生活環境の消毒やケアも行うことで再発を防ぎます。
脱毛の治療は、症状を一時的に抑えるだけでは根本的な解決にはなりません。特にアレルギー性皮膚炎や慢性的な疾患が原因の場合は、日々の継続的なケアが健康な被毛と皮膚を保つための重要なポイントです。
定期的に動物病院で検診を受け、症状の再発や悪化を防ぐことが大切です。
自宅でできるケア
診断と治療を受けることはもちろんですが、日常的に行うケアも愛猫の健康維持には欠かせません。
・日常的なブラッシング
ブラッシングは被毛を清潔に保つだけでなく、皮膚の血行を促し、健康な毛の成長を助ける効果があります。ブラッシングの際は、毛の流れに沿って優しく行うことが大切です。
特に抜け毛が多くなる換毛期には、ブラッシングの頻度を増やすことで毛玉の予防にもつながります。
・適切なシャンプーの選び方
猫の皮膚はとても繊細なので、シャンプー選びには注意が必要です。無香料で低刺激のものや、保湿成分が含まれた製品を選びましょう。シャンプーに迷った場合は、獣医師に相談して愛猫に合った商品を選ぶことが大切です。
・環境ストレスの軽減
ストレスは脱毛の大きな原因の一つです。愛猫が安心して過ごせるよう、生活環境を見直してみましょう。隠れ場所を用意する、騒音や急な変化を避けるなど、猫にとって落ち着ける環境を整えることが大切です。
また、他の家族との接触がストレスになっていないか、愛猫の様子をよく観察するようにしましょう。
・食事管理のポイント
栄養バランスの取れた食事は、健康な皮膚と被毛を保つための基本です。食事内容を変更する際は、かかりつけの獣医師に相談しながら進めることをおすすめします。
オメガ3脂肪酸や良質なタンパク質を含むフード、アレルギー対応のフードを試してみるのもよいでしょう。
また、水分をしっかり摂取できるよう、ウェットフードを取り入れた「ミックスフィーディング」も効果的です。
予防と対策
猫の脱毛を未然に防ぐためには、日頃からの予防と対策が大切です。以下のポイントを意識しながら、愛猫の健康を守っていきましょう。
<定期的な健康診断を受ける>
健康診断は脱毛や皮膚トラブルを早期に発見するための有効な手段です。潜在的な病気やホルモン異常など、皮膚のトラブルの背後に隠れている疾患を早期に見つけることができ、初期段階で治療を開始することで症状の悪化を防ぐことができます。
また、飼い主様が見逃してしまいがちな初期症状も、獣医師の診察によってしっかりとチェックすることが可能です。
<早期発見のためのチェックポイント>
日常生活の中で、愛猫の様子を次のポイントから観察する習慣をつけましょう。
・脱毛の形や範囲(円形脱毛や広範囲の脱毛など)
・皮膚の状態(赤み、フケ、湿疹の有無)
・毛を軽く引っ張った際の抜けやすさ
・かゆがる仕草や過剰な毛づくろいの有無
これらの変化に気づいた場合は、早めに動物病院を受診することが重要です。
<生活環境を整備する>
愛猫が快適に過ごせる環境を整えることも、脱毛予防の大切なポイントです。
・清潔な環境を保つ:ノミやダニの発生を防ぐために、寝具やケージ、愛猫の過ごす場所をこまめに掃除しましょう。
・適度な湿度の維持:室内が乾燥しすぎると皮膚トラブルの原因になります。湿度は40~60%に保つように心がけましょう。
・ストレスの軽減:静かで落ち着ける場所を用意し、急激な環境の変化や騒音を避けることが大切です。愛猫のリラックスできる環境づくりを意識しましょう。
<かかりつけ医への相談タイミング>
愛猫に脱毛や皮膚トラブルが見られた際、次のような場合には早めに動物病院への相談を検討してください。
・脱毛が数日経っても改善しない
・皮膚の赤みや湿疹が広がっている
・かゆみや痛みでストレスを感じている様子が見られる
・食欲不振や元気がないなど、他の症状が併発している
日頃から愛猫の様子を注意深く観察し、健康管理を徹底することで、脱毛や皮膚トラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ
猫の脱毛はさまざまな原因によって引き起こされますが、早期発見と適切なケアによって改善が期待できます。日頃から愛猫の様子をしっかり観察し、定期的な健康診断を受けることで、症状の早期発見や対処が可能です。
また、愛猫が快適に過ごせる環境を整えることも、脱毛予防には欠かせません。
少しでも異変に気づいたら、早めにかかりつけの獣医師に相談し、適切な対応を心がけましょう。
■関連する記事はこちらで解説しています
岡山県倉敷市にある「倉敷動物愛護病院」
ペットと飼い主様にとって最善の診療を行うことを心がけております。
一般診療はこちらから
獣医師コラム一覧
-
- 2025/12/16
- 犬や猫の噛み癖の理由や原因は?...
-
- 2025/12/16
- 犬猫のよだれが多いのは異常?正...
-
- 2025/12/09
- 犬の皮膚がカサカサ?秋冬の乾燥...
-
- 2025/12/02
- 犬と猫の頻尿・血尿・排尿困難に...
-
- 2025/10/06
- 猫が毛玉を吐くのは病気?|毛球...
-
- 2025/10/06
- ペットロスの向き合い方~飼い主...
-
- 2025/10/06
- 愛犬の歩き方がおかしい?犬の椎...
-
- 2025/10/06
- シニア犬、シニア猫(7歳以上)...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の成長に合わせた食事...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の「社会化期」にすべ...
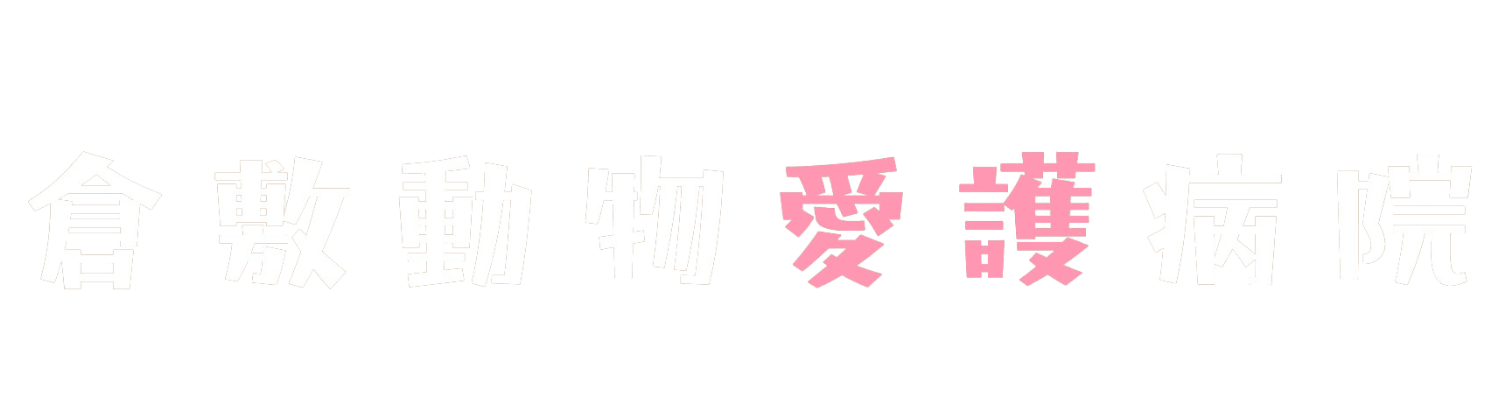
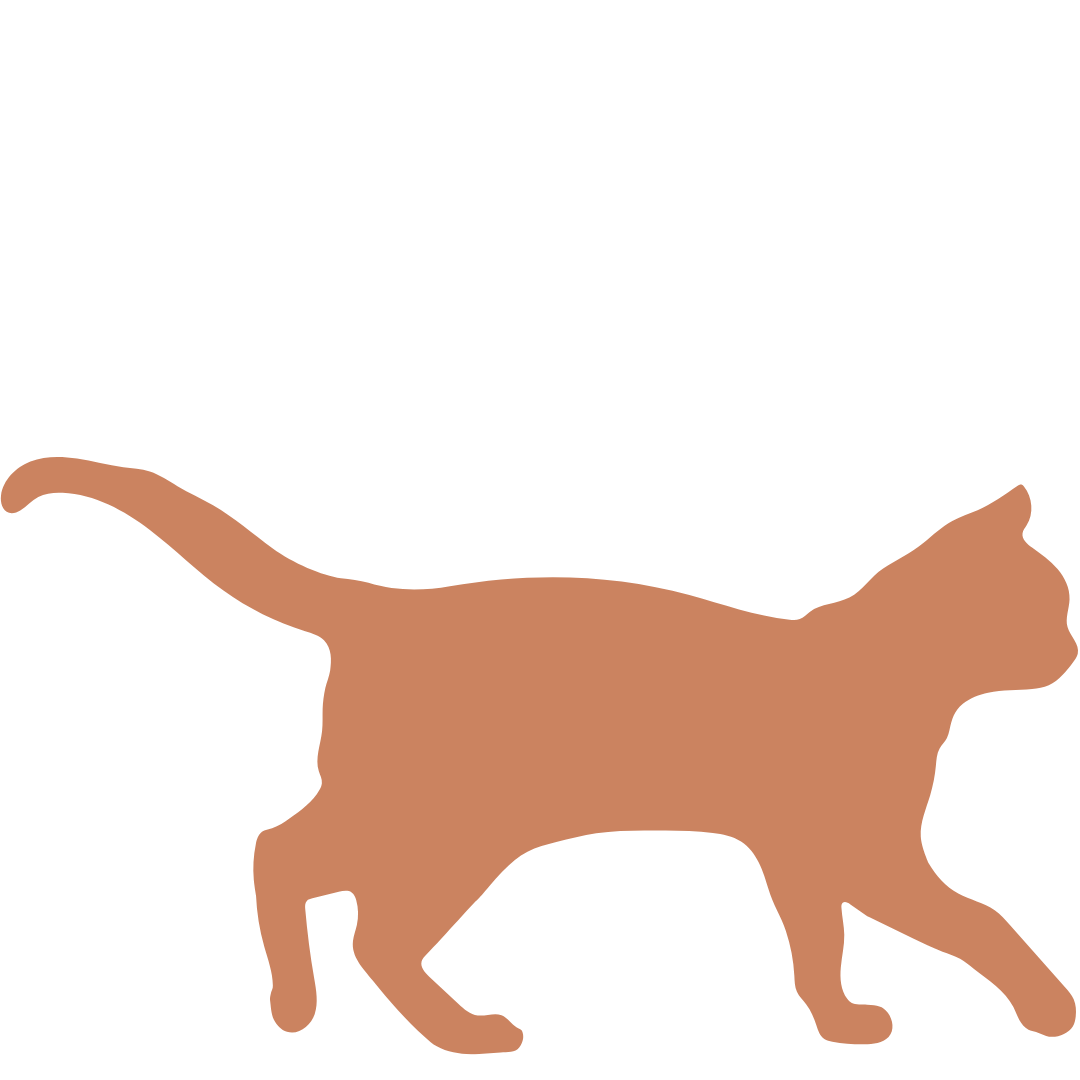
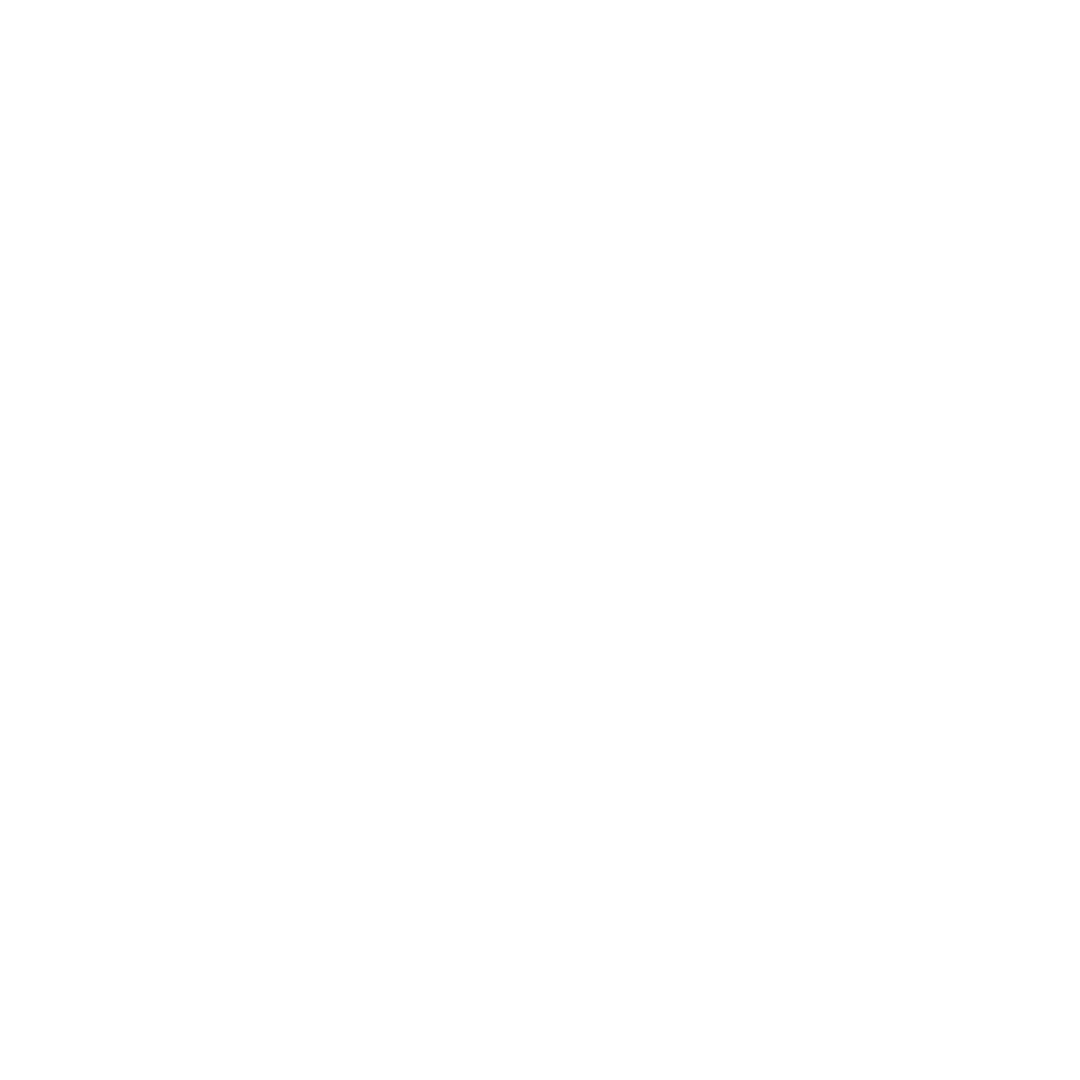
 インスタグラム
インスタグラム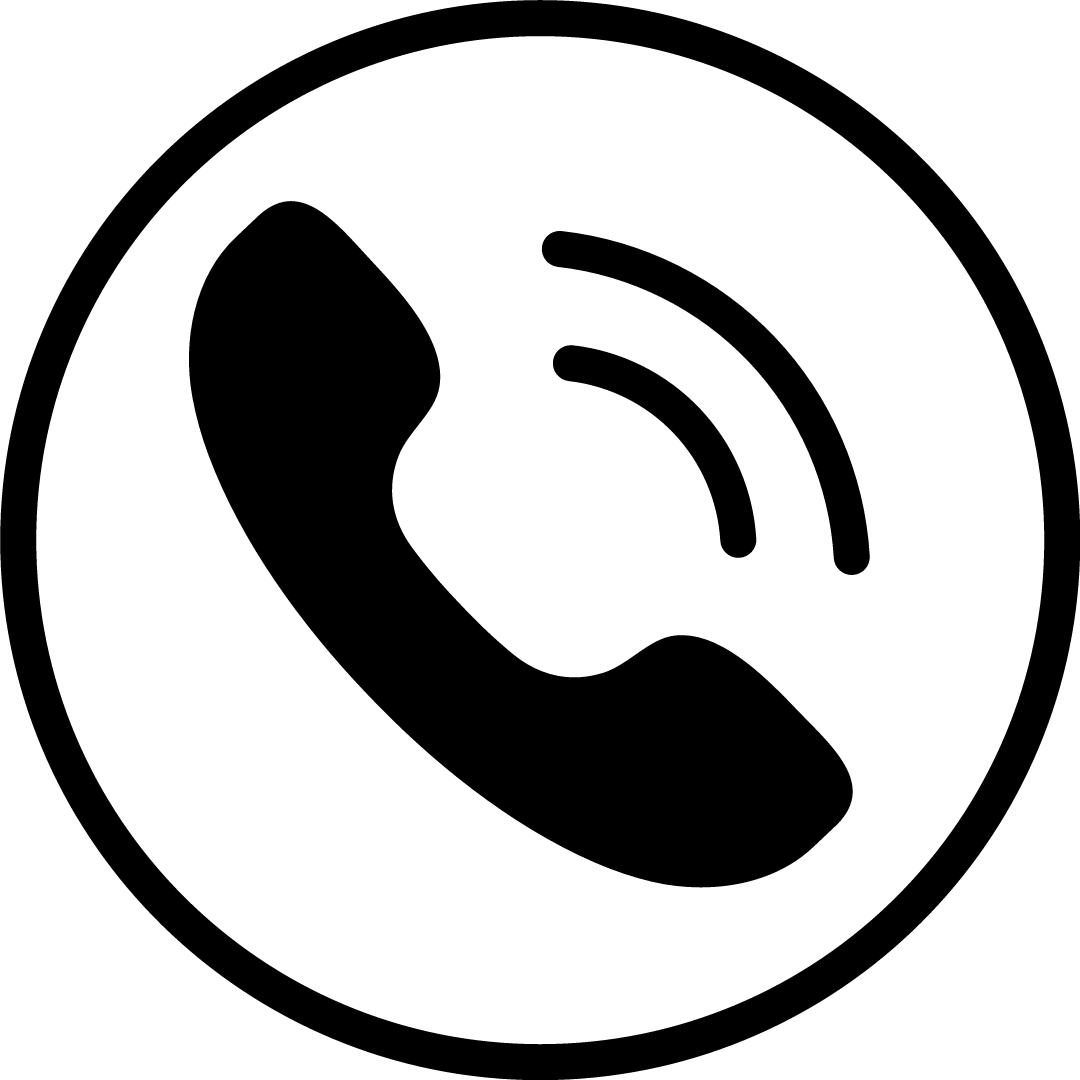 電話
電話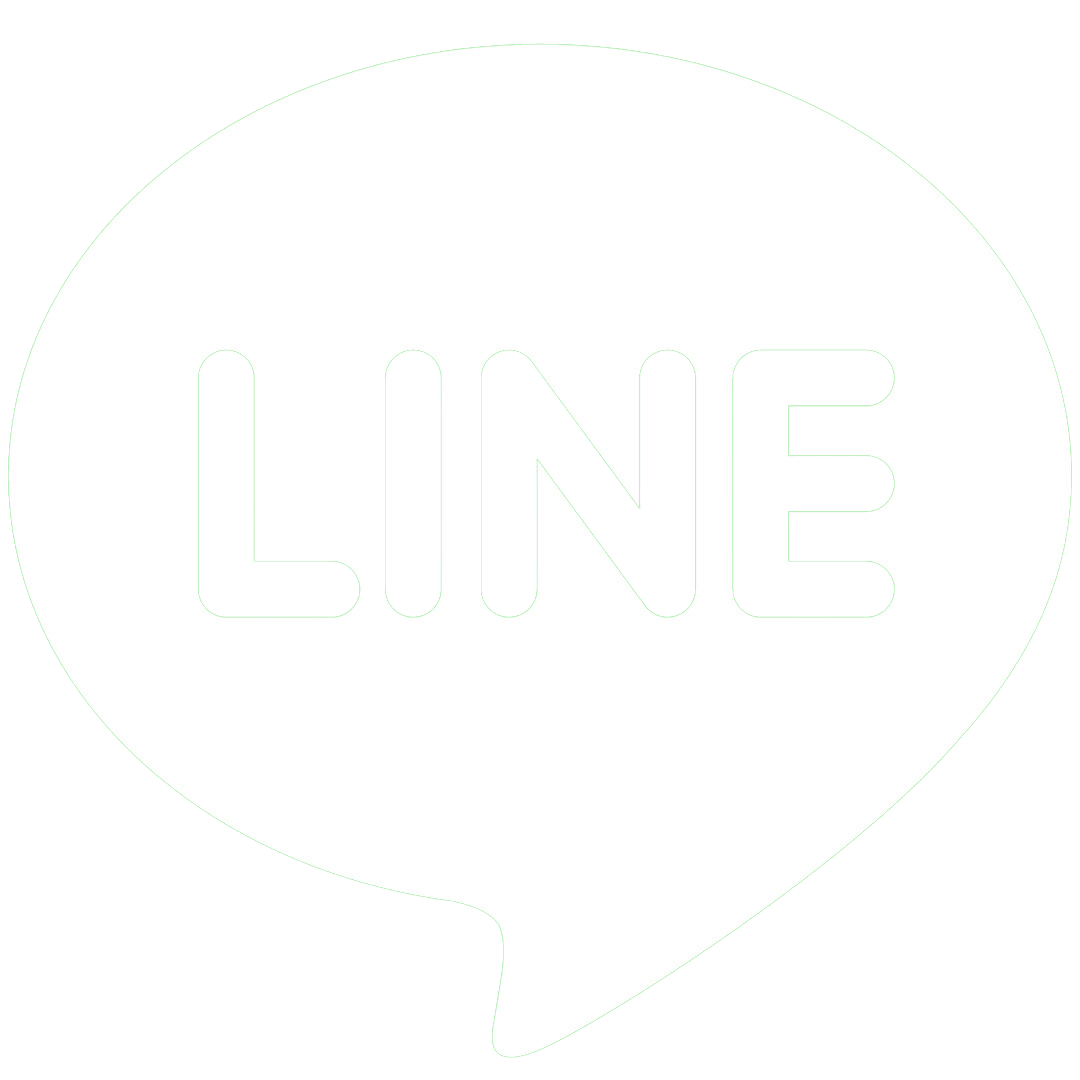 ライン予約はこちら
ライン予約はこちら