獣医師コラム一覧
-
- 2025/12/16
- 犬や猫の噛み癖の理由...
-
- 2025/12/16
- 犬猫のよだれが多いの...
-
- 2025/12/09
- 犬の皮膚がカサカサ?...
-
- 2025/12/02
- 犬と猫の頻尿・血尿・...
-
- 2025/10/06
- 猫が毛玉を吐くのは病...
-
- 2025/10/06
- ペットロスの向き合い...
-
- 2025/10/06
- 愛犬の歩き方がおかし...
-
- 2025/10/06
- シニア犬、シニア猫(...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の成長に合...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の「社会化...
獣医師コラム
マダニが媒介するSFTSについて|犬や猫、人への感染リスクと対策
倉敷市、岡山市、総社市、浅口市、玉野市、早島町の皆さんこんにちは。
岡山県倉敷市の倉敷動物愛護病院の院長垣野です。
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、マダニが媒介するウイルス感染症で、近年日本国内でも報告が増えている恐ろしい病気の一つです。
この病気は人に感染すると発熱や消化器症状を引き起こし、場合によっては重症化して命に関わることもあります。
SFTSは、何よりも「予防」が大切な病気です。正しい知識を持つことで、愛犬や愛猫、そして飼い主様ご自身の健康を守ることができます。
今回は、マダニが媒介するSFTSについて、症状の早期発見のポイントや具体的な予防方法を解説します。

■目次
1.マダニが運ぶSFTSとは?
2.主な症状と進行
3.診断方法
4.治療方法
5.マダニ予防がカギ!|SFTSから犬や猫を守る方法
6.もしもマダニが付いたら?|安全な対処法
7.まとめ
マダニが運ぶSFTSとは?
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、ウイルスによって引き起こされる感染症で、主にダニを介して広がります。感染したマダニに咬まれることでウイルスが体内に侵入し、発熱や下痢、血小板の減少など、さまざまな症状を引き起こします。
マダニは野山や草むら、公園などに多く生息しており、散歩や外で遊んでいるときに、気づかないうちに咬まれてしまうことがあります。特に暖かい季節になると、マダニの活動が活発になるため、感染リスクも高まります。
SFTSで特に注意したいのは「犬や猫から人への感染」のリスクです。
SFTSウイルスは、感染した犬や猫の血液や唾液などの体液を通じて人にもうつることがあります。そのため、愛犬や愛猫がSFTSを発症した場合は、飼い主様や獣医師も慎重に対応することが大切です。
主な症状と進行
SFTSの症状は初期段階では風邪に似ているため、見逃されてしまうことがあります。しかし、進行すると命に関わる重篤な状態になることもありますので、早期の気づきがとても大切です。
◆初期症状
SFTSに感染した犬や猫は発熱することが多く、食欲が落ちる、元気がなくなるなどの変化が見られます。普段は活発な愛犬が散歩を嫌がる場合や、大好きなごはんに興味を示さない場合は注意が必要です。
ただし、犬や猫では初期段階では無症状の場合も少なくありません。元気そうに見えても、実は体内で病気が進行している場合もあるため、油断は禁物です。
◆進行期の症状と重症化のリスク
病気が進行すると、血液の異常が現れることがあります。特に、血小板が減少すると、皮膚や口の中の粘膜に内出血が見られることがあります。
また、嘔吐や下痢などの消化器症状が悪化し、体内の水分が失われて脱水症状を引き起こす可能性もあります。
さらに進行が進むと、ふらつきやぼんやりした様子など、神経症状が見られることもあります。
SFTSは致死率が高く、特に免疫力が低下している犬や猫やシニアの場合は症状が急速に悪化
することがあります。適切な治療を受けられない場合、回復が難しくなることもあるため、早期発見と早期治療がとても大切です。
<SFTSと間違えやすい病気とは?>
SFTSと似た症状を示す病気はいくつか存在します。例えば、マダニが媒介するバベシア症やライム病、あるいは細菌性の敗血症なども考えられます。
診断方法
SFTSの診断には、いくつかの検査が必要です。発熱や食欲不振といった症状だけでは、SFTSかどうかを判断するのは難しいため、血液検査やPCR検査を組み合わせて、慎重に診断を行います。
◆血液検査
SFTSの感染が疑われる場合、まず血液検査を行い、血小板や白血球の減少、肝臓や腎臓の数値に異常がないかを確認します。
特に、血小板の減少や、CRPやSAAといった炎症マーカーの上昇が見られることが多く、これらの変化は診断の大きな手がかりとなります。
◆PCR検査
血液検査だけではSFTSと確定することが難しいため、さらにPCR検査を行います。この検査では、SFTSウイルスの遺伝子を調べ、ウイルスの存在を直接確認します。
PCR検査は感染の有無を正確に判断できるため、確定診断に欠かせない重要な検査です。
治療方法
SFTSには、現在のところ特効薬がありません。そのため、治療は主に対症療法を中心に行われます。
◆対症療法
発熱や消化器症状などのつらい症状を和らげるために、解熱剤や制吐薬、胃腸薬などを使用します。
◆入院管理
SFTSの症状が重い場合は、入院して治療を受けることが必要です。入院中は、点滴治療を行いながら、状態をしっかりと管理します。
特に、以下のような場合には、入院による集中的なケアが必要です。
・血小板が極端に低下している場合:出血しやすくなるため、内出血や出血の管理が重要です。
・重度の脱水がある場合:点滴を通じて水分や電解質を補い、体のバランスを整えます。
◆輸液療法(点滴治療)
SFTSに感染すると食欲不振や下痢、嘔吐といった症状が現れ、体の中の水分が不足して脱水症状を引き起こすことが多くあるため、輸液療法(点滴)を行い、体内に必要な水分や電解質を補います。
<治療後の回復について>
SFTSは致死率が高い病気の一つですが、早期に適切な治療を開始することで回復の可能性も十分にあります。
「いつもと様子が違うな」と感じたら、迷わず動物病院に相談し、適切な対応を受けることが大切です。
マダニ予防がカギ!|SFTSから犬や猫を守る方法
SFTSを予防するためには、マダニ対策が最も大切です。特に、草むらや公園などの屋外で遊ぶことが多い犬や猫は、定期的な予防を心がけることで、感染リスクを減らすことができます。
◆マダニ予防
マダニの付着を防ぐために、予防薬を定期的に使用することが効果的です。予防薬には、以下のような種類があります。
・スポットタイプ(背中にたらすタイプ):手軽に使えて、外出前にもさっと使用できます。
・飲み薬(内服タイプ):薬を飲むのが得意な子におすすめです。
・首輪タイプ(防虫首輪):長期間効果が持続し、アウトドアが多い動物に向いています。
どのタイプを選ぶかは、飼い主様の生活スタイルや、愛犬・愛猫の性格に合わせて選ぶことがポイントです。
多くの予防薬は月に1回の投与が基本となり、継続して使うことで効果を最大限に発揮しますので、忘れないようにカレンダーにメモしておくのもおすすめです。
◆環境対策
散歩コースや庭の環境を整えることも、SFTSの予防にはとても大切です。
マダニは、草むらや茂み、落ち葉の多い場所に潜んでいることが多いため、散歩の際はこうした場所への立ち入りをなるべく避けることで、感染リスクを減らすことができます。
また、お庭がある場合は、定期的に除草を行い、マダニが生息しにくい環境を整えましょう。
◆日常的な確認
外出から戻ったら、愛犬や愛猫の体にマダニが付いていないかチェックする習慣をつけましょう。特に、耳の裏や脇の下、股の部分など、毛が密集している場所はマダニが付きやすいので重点的にチェックしましょう。
もしもマダニが付いたら?|安全な対処法

万が一、愛犬や愛猫にマダニが付着してしまった場合は、動物病院で適切に処置を受けることが大切です。
マダニは皮膚にしっかりと噛みついて血を吸っているため、無理に引き剥がそうとすると、頭部が皮膚内に残ってしまうことがあります。また、素手で触ったり、マダニをつぶしたりすると、感染症のリスクがあるため注意が必要です。
動物病院では、専用の器具を使用して安全にマダニを取り除きます。無理に引き剥がさないように細心の注意を払いながら処置を行うため、マダニの口器が皮膚に残る心配がありません。また、必要に応じて、患部の消毒や抗炎症処置を行い、感染症のリスクを最小限に抑えます。
マダニを取り除いた後は、愛犬や愛猫の体調をよく観察しましょう。 特に、皮膚に赤みや腫れが続いていないか、元気や食欲が落ちていないかを注意深く見てください。
もし、咬んだ跡が炎症を起こしている場合や、発熱、元気消失、嘔吐や下痢などの症状が見られる場合は、早めに動物病院を受診しましょう。
まとめ
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、マダニを介して感染する危険なウイルス感染症です。犬や猫だけでなく、飼い主様にも影響を及ぼす可能性があるため、日常的なマダニ予防がとても大切です。
愛犬や愛猫の健康を守るためには、定期的に予防薬を使用することが効果的です。予防薬を継続して使用することで感染リスクを大幅に軽減できるため、忘れずに投与を続けましょう。
SFTSは、日常的な予防を心がけることで防ぐことができます。もしも「いつもと様子が違うな」と感じたときは、早めに動物病院にご相談ください。
■関連する記事はこちらから
・犬と猫のアトピー性皮膚炎について|痒みと皮膚トラブルの原因と対策
・犬と猫のアレルギー性皮膚炎について|皮膚トラブルの原因は?
岡山県倉敷市にある「倉敷動物愛護病院」
ペットと飼い主様にとって最善の診療を行うことを心がけております。
一般診療はこちらから
獣医師コラム一覧
-
- 2025/12/16
- 犬や猫の噛み癖の理由や原因は?...
-
- 2025/12/16
- 犬猫のよだれが多いのは異常?正...
-
- 2025/12/09
- 犬の皮膚がカサカサ?秋冬の乾燥...
-
- 2025/12/02
- 犬と猫の頻尿・血尿・排尿困難に...
-
- 2025/10/06
- 猫が毛玉を吐くのは病気?|毛球...
-
- 2025/10/06
- ペットロスの向き合い方~飼い主...
-
- 2025/10/06
- 愛犬の歩き方がおかしい?犬の椎...
-
- 2025/10/06
- シニア犬、シニア猫(7歳以上)...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の成長に合わせた食事...
-
- 2025/09/17
- 子犬・子猫の「社会化期」にすべ...
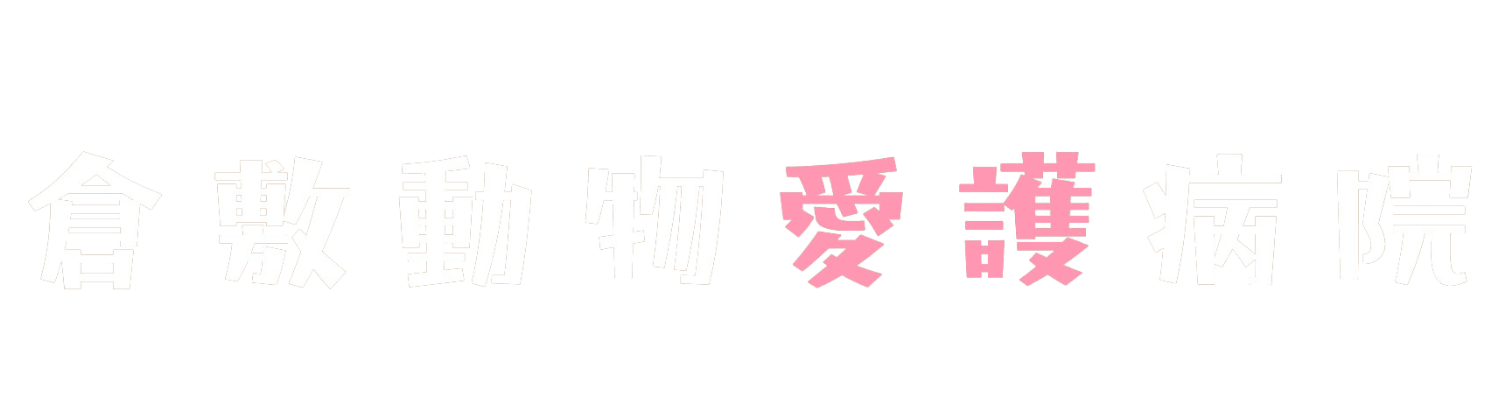
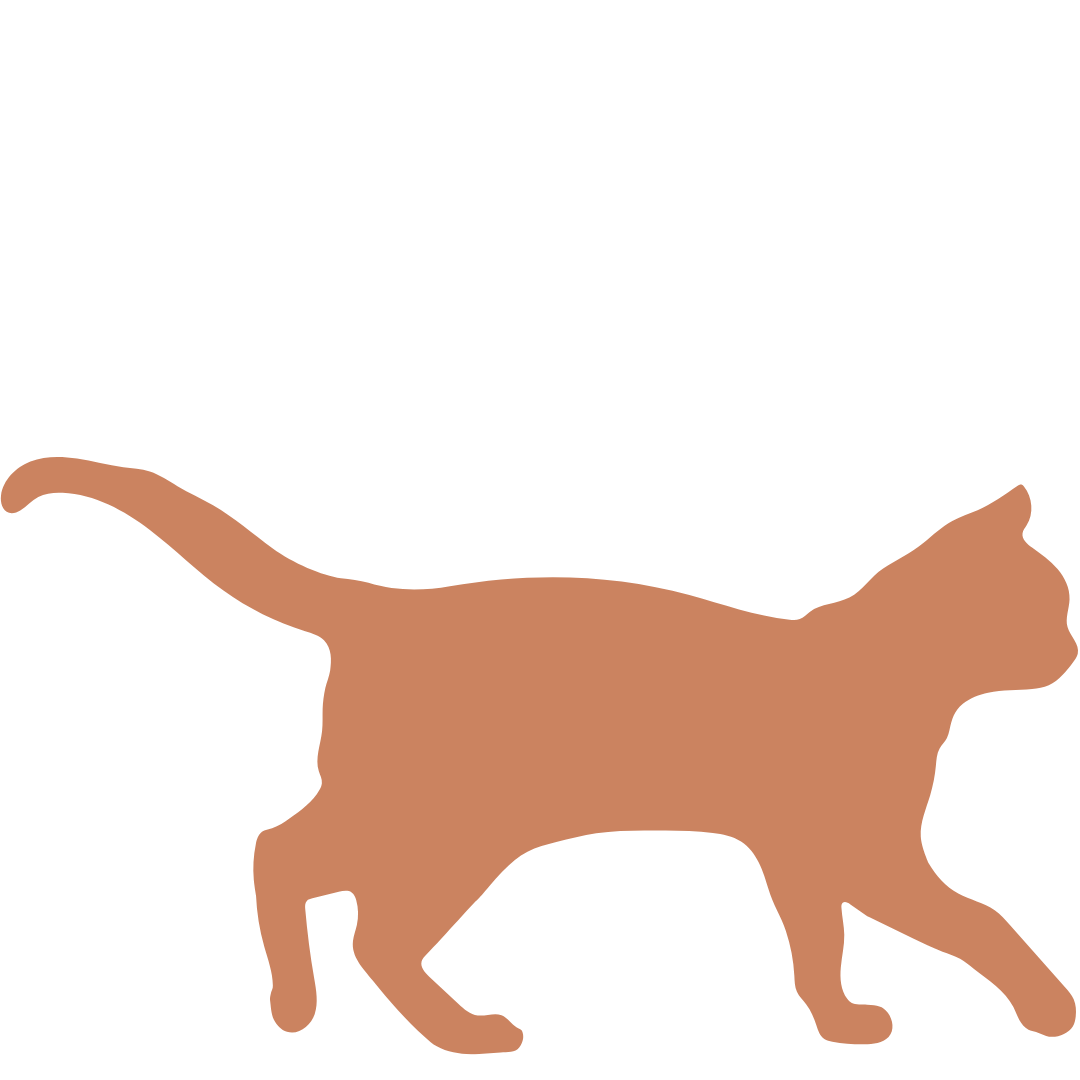
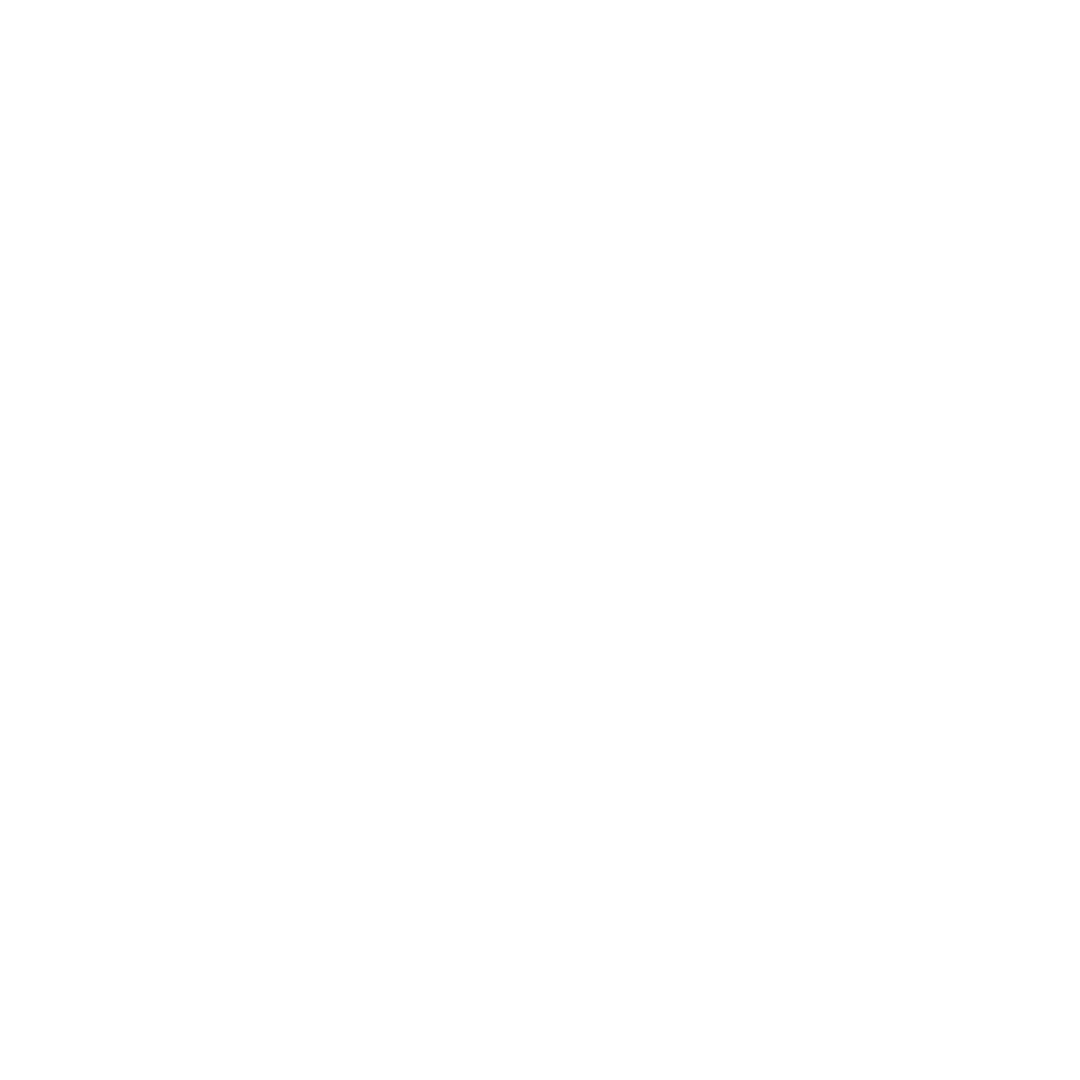
 インスタグラム
インスタグラム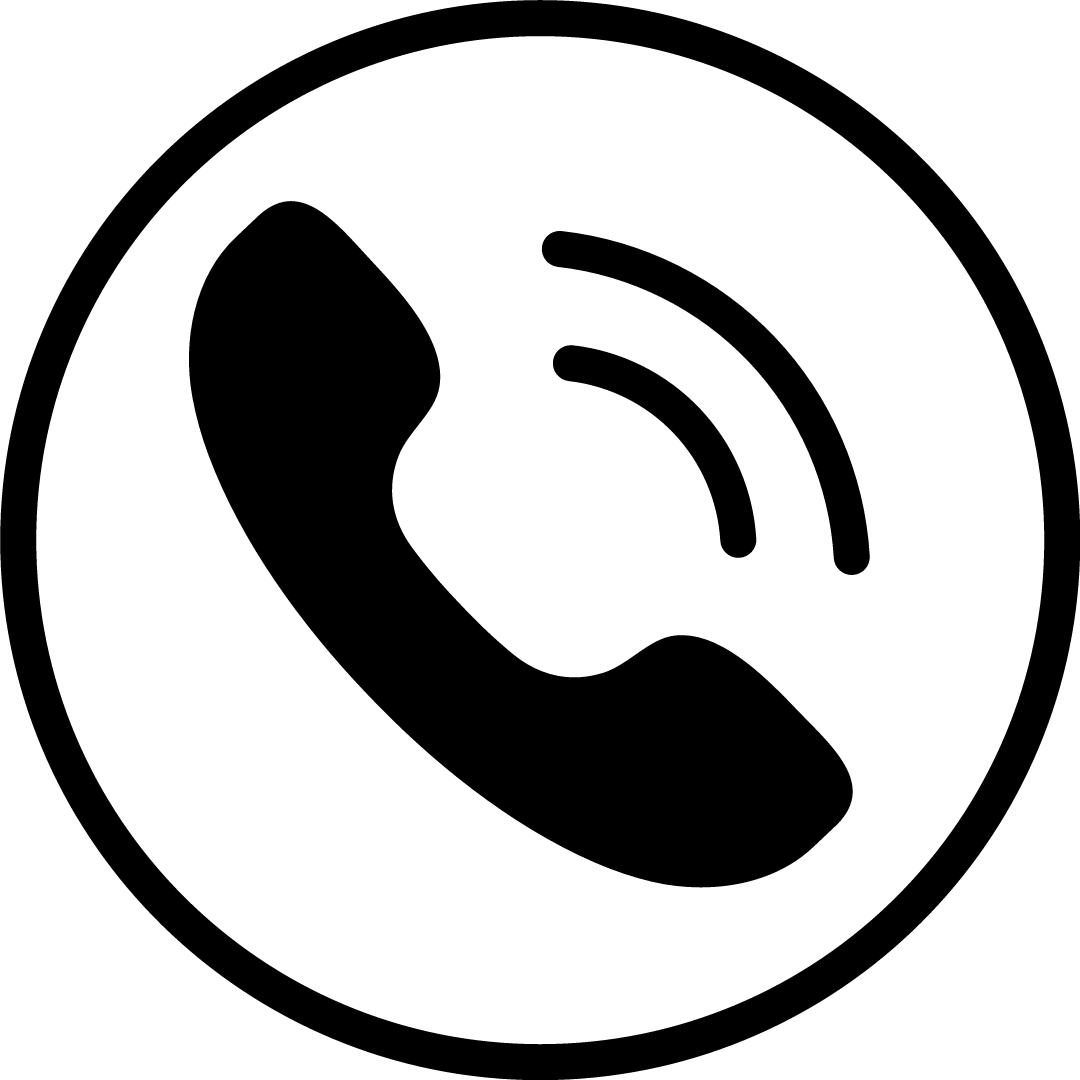 電話
電話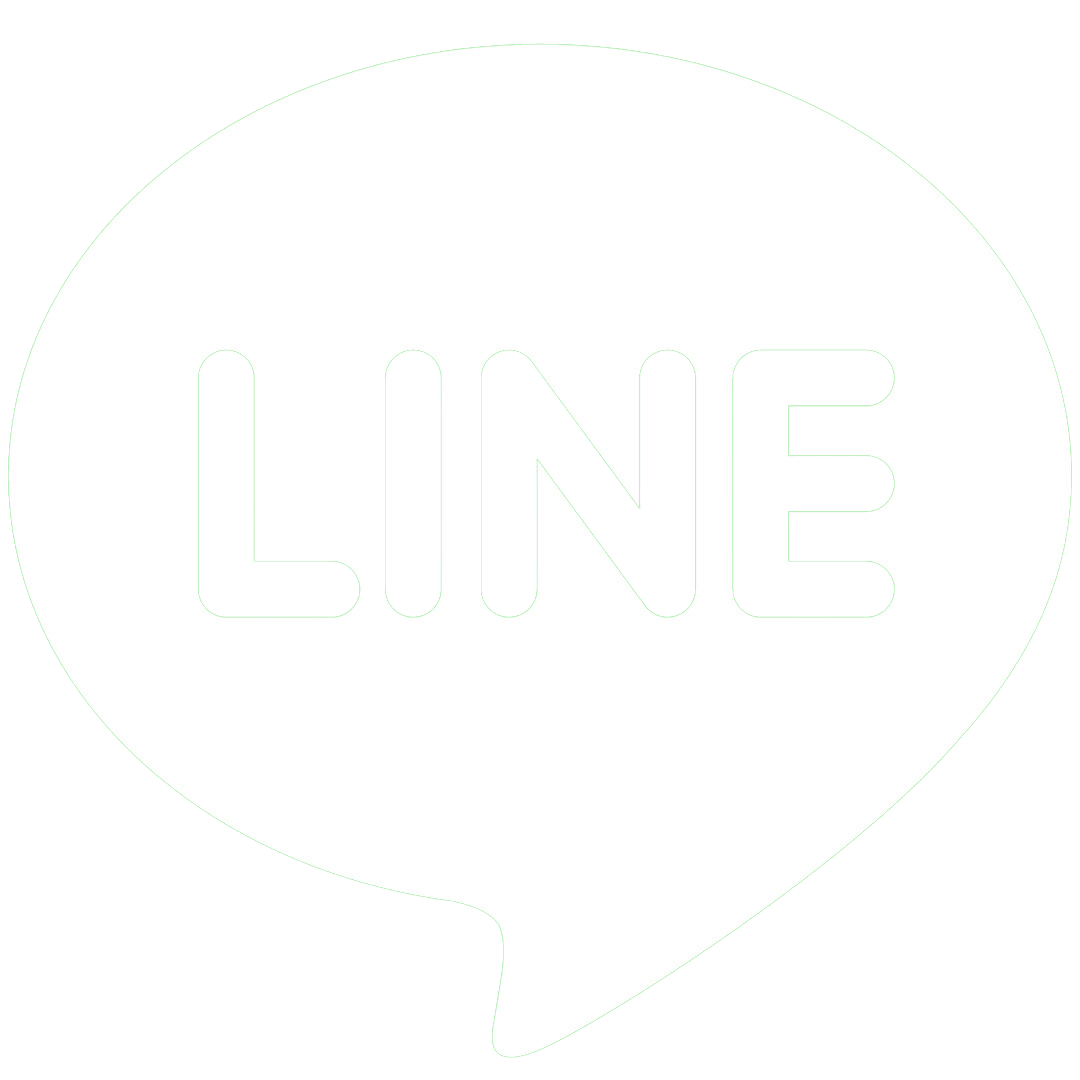 ライン予約はこちら
ライン予約はこちら